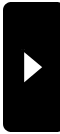2019年05月25日15:42
農地取得下限面積を30aに緩和、建設経済委員会報告≫
カテゴリー │議会活動
農地取得の下限面積を30アールに緩和
農地を耕作する目的で取得しようとする場合、農地法の許可が必要です。農地法の許可要件には、権利取得後の耕作面積が50a以上となるとの「下限面積」があります。平成21年12月施行の改正農地法により、地域の実情に合わない場合は農業委員会の判断で50aより少ない面積で設定できるようになり、平成31年3月の市農業委員会で農地の権利取得の要件を50aから30aに変更しました。
下限面積を緩和する理由は
農業者の高齢化・後継者不足等より農業者が減少、耕作放棄地の増加し深刻化。このため、小規模農家を含めた多様な農業者が農地取得できるように下限面積を緩和し、耕作放棄地発生の抑制、作業効率が低い集落内の狭小農地の耕作、退職後の就農など新規参入を図るためです。
変更内容
①区域の設定 市内全域
②別段の面積(下限面積)30アール
森林環境贈与税を活用した森林整備事業
背景と目的
森林は、地球温暖化防止や災害防止等多面的な機能を有し、その機能が十分発揮できるように適切な管理・整備が必要です。しかし、近年林業の担い手不足や高齢化、所有者不明森林の増加などによる森林の荒廃が大きな課題となっている。
森林環境贈与税・森林環境税は、こうした課題解決のため市町村が主体となり取り組む「新たな森林管理システム」への財源として創設されます。
森林環境贈与税
平成31年度から施行。森林環境税の相当額とし、課税前であるため国が借り入れを行い、都道府県及び市町村へ贈与する。
森林環境税
令和6年度から施行。個人へ国税として課税、年額1,000円。徴収課税は、市町村が個人住民税と併せて行う。市町村は、森林環境税として納付された額を国の交付税及び譲与税配当金特別会計に払い込む。その後特定財源化し、市町村に森林環境贈与税として配分される仕組み。
森林環境譲与税の算出基準
市町村分の算出割合は
50%:民有林人工林面積(袋井市内279㏊)
20%:林業就業者数(市内9名2事業所)
30%:人口
森林環境贈与税の試算
H31~R3年420万円/年、R4~R年 630万円/年、R6年650万円/年、R7~R10年930万円/年、R11~R14年1190万円/年、
R15年~1460万円/年
袋井市内の森林の状況
総面積10,856haのうち、森林面積は2,223ha。(民有林1,661ha、国有林373ha、県有林139ha、市有林50ha)で、総面積の20%。
「新たな森林管理システム」とは(自治体の責務)
市町村が仲介役となり、区域内の森林の経営管理を円滑に行うよう定められた「森林管理法」に基づく取り組みが求められる。(まずは意向調査の実施)
袋井市の森林環境譲与税を活用した事業
制度開始となる令和元年度から対象森林の現況を調査する「事前調査」を実施。「林地台帳管理システム」の情報更新を行う。また、海岸林松くい虫対策として捕植を検討、中長期的な木材利用事業への活用を図るため「基金」造成も検討する。
水道料金等懇話会の設置
平成27年2月12日に提言された「袋井市水道料金等懇話会意見書」では、「水道料金等の算定期間は平成28年度からの5年間とし、安定した事業経営を図るためには料金が適正なものであるか定期的検討が必要」とされている。
そのため、懇話会を設置し、2021年度以降の水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料について意見を取りまとめ、市長に提言する。
選任された懇話会委員
兼子文夫(あおぞら税理士法人取締役)、佐藤和美(静岡産業大学経営学部教授)、宮原高志(静岡大学学術院工学領域教授)、佐藤静夫(豊沢自治会連合会会長)、山田敏明(下山梨自治会連合会会長)、水谷欣志(袋井商工会議所会頭)、川上政年(浅羽町商工会会長)、村田朝子(NPO法人プライツ理事長)、榛葉美希(袋井青年会議所常任理事)
スケジュール 6回の懇話会を開催し、2020年3月市長に意見書を提出する予定です。
農地を耕作する目的で取得しようとする場合、農地法の許可が必要です。農地法の許可要件には、権利取得後の耕作面積が50a以上となるとの「下限面積」があります。平成21年12月施行の改正農地法により、地域の実情に合わない場合は農業委員会の判断で50aより少ない面積で設定できるようになり、平成31年3月の市農業委員会で農地の権利取得の要件を50aから30aに変更しました。
下限面積を緩和する理由は
農業者の高齢化・後継者不足等より農業者が減少、耕作放棄地の増加し深刻化。このため、小規模農家を含めた多様な農業者が農地取得できるように下限面積を緩和し、耕作放棄地発生の抑制、作業効率が低い集落内の狭小農地の耕作、退職後の就農など新規参入を図るためです。
変更内容
①区域の設定 市内全域
②別段の面積(下限面積)30アール
森林環境贈与税を活用した森林整備事業
背景と目的
森林は、地球温暖化防止や災害防止等多面的な機能を有し、その機能が十分発揮できるように適切な管理・整備が必要です。しかし、近年林業の担い手不足や高齢化、所有者不明森林の増加などによる森林の荒廃が大きな課題となっている。
森林環境贈与税・森林環境税は、こうした課題解決のため市町村が主体となり取り組む「新たな森林管理システム」への財源として創設されます。
森林環境贈与税
平成31年度から施行。森林環境税の相当額とし、課税前であるため国が借り入れを行い、都道府県及び市町村へ贈与する。
森林環境税
令和6年度から施行。個人へ国税として課税、年額1,000円。徴収課税は、市町村が個人住民税と併せて行う。市町村は、森林環境税として納付された額を国の交付税及び譲与税配当金特別会計に払い込む。その後特定財源化し、市町村に森林環境贈与税として配分される仕組み。
森林環境譲与税の算出基準
市町村分の算出割合は
50%:民有林人工林面積(袋井市内279㏊)
20%:林業就業者数(市内9名2事業所)
30%:人口
森林環境贈与税の試算
H31~R3年420万円/年、R4~R年 630万円/年、R6年650万円/年、R7~R10年930万円/年、R11~R14年1190万円/年、
R15年~1460万円/年
袋井市内の森林の状況
総面積10,856haのうち、森林面積は2,223ha。(民有林1,661ha、国有林373ha、県有林139ha、市有林50ha)で、総面積の20%。
「新たな森林管理システム」とは(自治体の責務)
市町村が仲介役となり、区域内の森林の経営管理を円滑に行うよう定められた「森林管理法」に基づく取り組みが求められる。(まずは意向調査の実施)
袋井市の森林環境譲与税を活用した事業
制度開始となる令和元年度から対象森林の現況を調査する「事前調査」を実施。「林地台帳管理システム」の情報更新を行う。また、海岸林松くい虫対策として捕植を検討、中長期的な木材利用事業への活用を図るため「基金」造成も検討する。
水道料金等懇話会の設置
平成27年2月12日に提言された「袋井市水道料金等懇話会意見書」では、「水道料金等の算定期間は平成28年度からの5年間とし、安定した事業経営を図るためには料金が適正なものであるか定期的検討が必要」とされている。
そのため、懇話会を設置し、2021年度以降の水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料について意見を取りまとめ、市長に提言する。
選任された懇話会委員
兼子文夫(あおぞら税理士法人取締役)、佐藤和美(静岡産業大学経営学部教授)、宮原高志(静岡大学学術院工学領域教授)、佐藤静夫(豊沢自治会連合会会長)、山田敏明(下山梨自治会連合会会長)、水谷欣志(袋井商工会議所会頭)、川上政年(浅羽町商工会会長)、村田朝子(NPO法人プライツ理事長)、榛葉美希(袋井青年会議所常任理事)
スケジュール 6回の懇話会を開催し、2020年3月市長に意見書を提出する予定です。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。