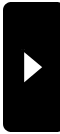2025年02月20日17:07
地震対策を進め、安心安全な袋井市を≫
カテゴリー │令和7年袋井市議選政策
みなさん。阪神大震災から30年、東日本大震災から14年が経過しました。しかしその教訓が能登半島地震では生かされておりません。昨年の元旦に発生した能登半島地震は、過去の震災と比べ突出して復旧・復興に遅れが生じています。すでに1年以上たちながら、半島という地形的問題もあり、豪雨災害の追い打ちもあって、道路や水道などの復旧も進まず、仮設住宅の建設も遅れ、いまだに避難生活を強いられている方もいます。能登半島では人口流出と災害関連死が続いており、課題は山積みとなっています。決して他人事として見過ごすわけにはまいりません。巨額の軍事費や無駄な関西万博に予算を積み込むのではなく、能登半島の復旧・復興こそ優先すべきではないでしょうか。
みなさん。発生当初避難生活を送る日本の避難所は国際基準に照らして大きく遅れています。トイレの数や被災者一人当たりの面積、温かい食事を提供するキッチンカー、段ボールベットの配備など、ハード・ソフトを含め見直しが求められています。しかし、運営主体となる市町村だけでは限界があります。国は財政面でも支援すべきです。
また仮設住宅建設の遅れ、家屋の被害判定の多くを担う自治体職員が市町村合併や公務員減らしによる人手不足で遅れが目立ち、現行制度の枠内では家屋が半壊以下の判定では仮設住宅に入れず、公費解体、医療費減免も受けられません。住宅を再建するにしても現状の補助金300万円では目途が立ちません。国は早急に2倍に引き上げるべきです。住宅の耐震化、液状化対策、上水道・下水道の耐震化など課題は山積みです。袋井市も能登半島地震の教訓を学び防災対策の見直し拡充を進めることが必要と考えます。
みなさん。政府の地震調査委員会はマグニチュード8~9程度を想定する南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率を「80%程度」に引き上げました。昭和19年(1944年)静岡県など東海地方を襲った「昭和東南海地震」の発生から80年がたち、いつ起きても不思議ではないとされる時期になっています。過去のデータ分析によれば袋井市の震度7だったとされ、多くの建物が倒壊、袋井町では67人が犠牲になったと記録もあります。三川地区でも小学生の犠牲者が出ています。市には災害発生を想定し、しっかりと準備を進めることを求めます。
みなさん。東南海地震が発生すれば、袋井市では沿岸部で津波被害が、平野部では川沿いの低地や沿岸部などに軟弱地盤が多く建物被害が心配されます。東南海地震は被災地が広範囲に及ぶとされ支援の手が届くことが危ぶまれます。圧倒的に支援のマンパワーも不足します。いかに支援が届くまで自助努力でつなぐことができるかが鍵となります。
みなさん。公助に頼るのではなく、自助共助を含め、今からしっかり準備を進めようではありませんか。
みなさん。発生当初避難生活を送る日本の避難所は国際基準に照らして大きく遅れています。トイレの数や被災者一人当たりの面積、温かい食事を提供するキッチンカー、段ボールベットの配備など、ハード・ソフトを含め見直しが求められています。しかし、運営主体となる市町村だけでは限界があります。国は財政面でも支援すべきです。
また仮設住宅建設の遅れ、家屋の被害判定の多くを担う自治体職員が市町村合併や公務員減らしによる人手不足で遅れが目立ち、現行制度の枠内では家屋が半壊以下の判定では仮設住宅に入れず、公費解体、医療費減免も受けられません。住宅を再建するにしても現状の補助金300万円では目途が立ちません。国は早急に2倍に引き上げるべきです。住宅の耐震化、液状化対策、上水道・下水道の耐震化など課題は山積みです。袋井市も能登半島地震の教訓を学び防災対策の見直し拡充を進めることが必要と考えます。
みなさん。政府の地震調査委員会はマグニチュード8~9程度を想定する南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率を「80%程度」に引き上げました。昭和19年(1944年)静岡県など東海地方を襲った「昭和東南海地震」の発生から80年がたち、いつ起きても不思議ではないとされる時期になっています。過去のデータ分析によれば袋井市の震度7だったとされ、多くの建物が倒壊、袋井町では67人が犠牲になったと記録もあります。三川地区でも小学生の犠牲者が出ています。市には災害発生を想定し、しっかりと準備を進めることを求めます。
みなさん。東南海地震が発生すれば、袋井市では沿岸部で津波被害が、平野部では川沿いの低地や沿岸部などに軟弱地盤が多く建物被害が心配されます。東南海地震は被災地が広範囲に及ぶとされ支援の手が届くことが危ぶまれます。圧倒的に支援のマンパワーも不足します。いかに支援が届くまで自助努力でつなぐことができるかが鍵となります。
みなさん。公助に頼るのではなく、自助共助を含め、今からしっかり準備を進めようではありませんか。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。