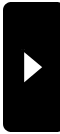2012年08月03日06:01

8月2日、袋井市・森町議会議員研修会が開かれました。今回の講師は、防災システム研究所所長山村武彦氏で「近助の精神・防災隣組」と題して講演されました。TV等でも出演する著名な講師ということで、議員に限らず市の幹部職員、自治会連合会長の参加を求め一緒に聴講していただきました。
山村氏は、これまで150か所以上の災害現地調査を実施、阪神大震災でも東日本大震災でも被災直後の現地に入ってつぶさに調査をし問題点を明らかにしてきました。今回はそうした現地の話を交えて実践的なお話をして頂きました。 東日本大震災で問われた7つのポイントとして、①災害想定や過去の経験にとらわれないこと、②緊急度・重要度+結果の重要性を考えた対策や行動に優先順位がある、③食料や防災史剤の備蓄などは家庭企業などと役割分担をはかる、④有事の際の人の心理的バイアスに配慮した防災教育をすること、⑤被災直後最も頼りになるのは近助の人で防災隣組が重要、⑦防災の知識習得や意識啓発など防災リテラシーを高めること、をあげられました。そして石巻市の大川小学校では過去の経験にとらわれて避難がおくれたこと、宮古市の田老堤防は壊れたがそれなりの役割を果たした。津波てんでんこの教訓を引き継ぎ、明治の15m高の津波で1859人死亡、昭和の津波で911人が死亡、今回は津波高18mで190人の死亡というように経験を生かして被害を減らした。要は心の堤防を高くすること、意識啓発の重要性を指摘しました。
今後の実践的対策として、防災心理を組み込んだ防災・危機管理マニュアルの再点検、普遍的、最大公約数の災害想定に基づいたもので実践的訓練を行うこと、自治体が全てを請け負うのではなく、近助の精神を活かした防災隣組を作ることなどわかりやすく解説してくれました。この講演をきいて自治体の防災対策とは、議員の役割とは何か、私自身何をなすべきか方向性が見えたような気がしました。
防災アドバイザー山村武彦氏の講演。≫
カテゴリー │議会活動

8月2日、袋井市・森町議会議員研修会が開かれました。今回の講師は、防災システム研究所所長山村武彦氏で「近助の精神・防災隣組」と題して講演されました。TV等でも出演する著名な講師ということで、議員に限らず市の幹部職員、自治会連合会長の参加を求め一緒に聴講していただきました。
山村氏は、これまで150か所以上の災害現地調査を実施、阪神大震災でも東日本大震災でも被災直後の現地に入ってつぶさに調査をし問題点を明らかにしてきました。今回はそうした現地の話を交えて実践的なお話をして頂きました。 東日本大震災で問われた7つのポイントとして、①災害想定や過去の経験にとらわれないこと、②緊急度・重要度+結果の重要性を考えた対策や行動に優先順位がある、③食料や防災史剤の備蓄などは家庭企業などと役割分担をはかる、④有事の際の人の心理的バイアスに配慮した防災教育をすること、⑤被災直後最も頼りになるのは近助の人で防災隣組が重要、⑦防災の知識習得や意識啓発など防災リテラシーを高めること、をあげられました。そして石巻市の大川小学校では過去の経験にとらわれて避難がおくれたこと、宮古市の田老堤防は壊れたがそれなりの役割を果たした。津波てんでんこの教訓を引き継ぎ、明治の15m高の津波で1859人死亡、昭和の津波で911人が死亡、今回は津波高18mで190人の死亡というように経験を生かして被害を減らした。要は心の堤防を高くすること、意識啓発の重要性を指摘しました。
今後の実践的対策として、防災心理を組み込んだ防災・危機管理マニュアルの再点検、普遍的、最大公約数の災害想定に基づいたもので実践的訓練を行うこと、自治体が全てを請け負うのではなく、近助の精神を活かした防災隣組を作ることなどわかりやすく解説してくれました。この講演をきいて自治体の防災対策とは、議員の役割とは何か、私自身何をなすべきか方向性が見えたような気がしました。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。