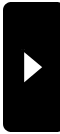2025年02月20日 17:22
早期に敷地川本格改修工事の着工完成を≫
カテゴリー │令和7年袋井市議選政策
豪雨被害防止対策・早期に敷地川本格改修工事の着工完成を
さてみなさん。異常な豪雨、台風、猛暑など地球温暖化がもたらす気候危機が世界で大問題となっています。近年、日本各地で記録的な大雨による土砂災害や河川の氾濫など大きな被害が発生しています。原因である二酸化炭素(CO²)の排出をどう減らすかにかかっていることはもちろんですが、気象災害の激甚化に対応し、災害から住民の命と財産をいかに守っていくのかの対策が求められています。
みなさん。低地が多い袋井市では、毎年のように市内各所で内水氾濫が起こっております。特に近年排水機能の不足している駅南地域では浸水被害が何回も発生、市は抜本的解消のため都市型排水機場の建設を計画しています。
私の住む三川地区では、2021年2022年2023年と豪雨により敷地川堤防が連続して被害を受けました。中でも2022年9月の台風15号の接近により線状降水帯が発生し、一日累計321㎜もの豪雨に見舞われました。それにより何か所も越水し、また漏水も発生、氾濫寸前ともいえる状況まできました。また山あいからの水がはけ切れず堤防西側の各所で住宅の浸水被害も発生しました。土砂崩れも何か所も発生し、長い期間不通となった道路もあり不便を要しました。
みなさん。現在も敷地川では応急復旧工事が進められていますが、あくまで緊急対応の工事であり私は全く不十分であると考えております。まず、不足している河道の拡張も不十分で、コンクリートによる護岸補強工事もされておりません。これではまた同様の豪雨に見舞われれば大変な事態を招きかけません。敷地川に隣接する住民は常に不安を抱えており抜本的改修を望んでいます。また越水の原因ともなっている橋梁の橋脚をなくすため橋梁の架け替え工事も進めることも必要事項と考えています。
みなさん。私は、改修計画がありながら長い年月先送りされてきた敷地川の本格的改修の早期着工の実現のため、三川地区住民が一丸となって要請行動を行うことが必要だと考えております。現に被害により移転した方もおります。みんなが安心して住み続けることができる三川地区とするため、みなさん一緒に運動をすすめようではありませんか。
私はその先頭に立って頑張る決意です。みなさまのご支援をお願いします。
さてみなさん。異常な豪雨、台風、猛暑など地球温暖化がもたらす気候危機が世界で大問題となっています。近年、日本各地で記録的な大雨による土砂災害や河川の氾濫など大きな被害が発生しています。原因である二酸化炭素(CO²)の排出をどう減らすかにかかっていることはもちろんですが、気象災害の激甚化に対応し、災害から住民の命と財産をいかに守っていくのかの対策が求められています。
みなさん。低地が多い袋井市では、毎年のように市内各所で内水氾濫が起こっております。特に近年排水機能の不足している駅南地域では浸水被害が何回も発生、市は抜本的解消のため都市型排水機場の建設を計画しています。
私の住む三川地区では、2021年2022年2023年と豪雨により敷地川堤防が連続して被害を受けました。中でも2022年9月の台風15号の接近により線状降水帯が発生し、一日累計321㎜もの豪雨に見舞われました。それにより何か所も越水し、また漏水も発生、氾濫寸前ともいえる状況まできました。また山あいからの水がはけ切れず堤防西側の各所で住宅の浸水被害も発生しました。土砂崩れも何か所も発生し、長い期間不通となった道路もあり不便を要しました。
みなさん。現在も敷地川では応急復旧工事が進められていますが、あくまで緊急対応の工事であり私は全く不十分であると考えております。まず、不足している河道の拡張も不十分で、コンクリートによる護岸補強工事もされておりません。これではまた同様の豪雨に見舞われれば大変な事態を招きかけません。敷地川に隣接する住民は常に不安を抱えており抜本的改修を望んでいます。また越水の原因ともなっている橋梁の橋脚をなくすため橋梁の架け替え工事も進めることも必要事項と考えています。
みなさん。私は、改修計画がありながら長い年月先送りされてきた敷地川の本格的改修の早期着工の実現のため、三川地区住民が一丸となって要請行動を行うことが必要だと考えております。現に被害により移転した方もおります。みんなが安心して住み続けることができる三川地区とするため、みなさん一緒に運動をすすめようではありませんか。
私はその先頭に立って頑張る決意です。みなさまのご支援をお願いします。
2025年02月20日 17:10
浜岡原発の再稼働は絶対に許してはならない≫
カテゴリー │令和7年袋井市議選政策
浜岡原発の再稼働は絶対に許してはならない
みなさん。地震と津波は収まれば故郷に戻れます。故郷まで失うのが原発災害です。東京電力福島第一原発の事故が物語っています。地震大国で原発はありえません。事故が起きてから「想定外だった」などということは二度とゆるされません。浜岡原発は震源域の真上にあり、「世界で一番厳しいところにある原発」と言われています。能登半島地震の際、避難計画の危うさが露呈しました。志賀原発周辺では道路の寸断や建物の損壊により孤立する集落もあり避難計画の懸念が露わとなりました。
みなさん。浜岡原発の再稼働は絶対に許してはなりません。大場袋井市長にも原発への認識を改めてもらい、再稼働反対の立場を明確に示すことを求めましょう。
みなさん。地震と津波は収まれば故郷に戻れます。故郷まで失うのが原発災害です。東京電力福島第一原発の事故が物語っています。地震大国で原発はありえません。事故が起きてから「想定外だった」などということは二度とゆるされません。浜岡原発は震源域の真上にあり、「世界で一番厳しいところにある原発」と言われています。能登半島地震の際、避難計画の危うさが露呈しました。志賀原発周辺では道路の寸断や建物の損壊により孤立する集落もあり避難計画の懸念が露わとなりました。
みなさん。浜岡原発の再稼働は絶対に許してはなりません。大場袋井市長にも原発への認識を改めてもらい、再稼働反対の立場を明確に示すことを求めましょう。
2025年02月20日 17:07
地震対策を進め、安心安全な袋井市を≫
カテゴリー │令和7年袋井市議選政策
みなさん。阪神大震災から30年、東日本大震災から14年が経過しました。しかしその教訓が能登半島地震では生かされておりません。昨年の元旦に発生した能登半島地震は、過去の震災と比べ突出して復旧・復興に遅れが生じています。すでに1年以上たちながら、半島という地形的問題もあり、豪雨災害の追い打ちもあって、道路や水道などの復旧も進まず、仮設住宅の建設も遅れ、いまだに避難生活を強いられている方もいます。能登半島では人口流出と災害関連死が続いており、課題は山積みとなっています。決して他人事として見過ごすわけにはまいりません。巨額の軍事費や無駄な関西万博に予算を積み込むのではなく、能登半島の復旧・復興こそ優先すべきではないでしょうか。
みなさん。発生当初避難生活を送る日本の避難所は国際基準に照らして大きく遅れています。トイレの数や被災者一人当たりの面積、温かい食事を提供するキッチンカー、段ボールベットの配備など、ハード・ソフトを含め見直しが求められています。しかし、運営主体となる市町村だけでは限界があります。国は財政面でも支援すべきです。
また仮設住宅建設の遅れ、家屋の被害判定の多くを担う自治体職員が市町村合併や公務員減らしによる人手不足で遅れが目立ち、現行制度の枠内では家屋が半壊以下の判定では仮設住宅に入れず、公費解体、医療費減免も受けられません。住宅を再建するにしても現状の補助金300万円では目途が立ちません。国は早急に2倍に引き上げるべきです。住宅の耐震化、液状化対策、上水道・下水道の耐震化など課題は山積みです。袋井市も能登半島地震の教訓を学び防災対策の見直し拡充を進めることが必要と考えます。
みなさん。政府の地震調査委員会はマグニチュード8~9程度を想定する南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率を「80%程度」に引き上げました。昭和19年(1944年)静岡県など東海地方を襲った「昭和東南海地震」の発生から80年がたち、いつ起きても不思議ではないとされる時期になっています。過去のデータ分析によれば袋井市の震度7だったとされ、多くの建物が倒壊、袋井町では67人が犠牲になったと記録もあります。三川地区でも小学生の犠牲者が出ています。市には災害発生を想定し、しっかりと準備を進めることを求めます。
みなさん。東南海地震が発生すれば、袋井市では沿岸部で津波被害が、平野部では川沿いの低地や沿岸部などに軟弱地盤が多く建物被害が心配されます。東南海地震は被災地が広範囲に及ぶとされ支援の手が届くことが危ぶまれます。圧倒的に支援のマンパワーも不足します。いかに支援が届くまで自助努力でつなぐことができるかが鍵となります。
みなさん。公助に頼るのではなく、自助共助を含め、今からしっかり準備を進めようではありませんか。
みなさん。発生当初避難生活を送る日本の避難所は国際基準に照らして大きく遅れています。トイレの数や被災者一人当たりの面積、温かい食事を提供するキッチンカー、段ボールベットの配備など、ハード・ソフトを含め見直しが求められています。しかし、運営主体となる市町村だけでは限界があります。国は財政面でも支援すべきです。
また仮設住宅建設の遅れ、家屋の被害判定の多くを担う自治体職員が市町村合併や公務員減らしによる人手不足で遅れが目立ち、現行制度の枠内では家屋が半壊以下の判定では仮設住宅に入れず、公費解体、医療費減免も受けられません。住宅を再建するにしても現状の補助金300万円では目途が立ちません。国は早急に2倍に引き上げるべきです。住宅の耐震化、液状化対策、上水道・下水道の耐震化など課題は山積みです。袋井市も能登半島地震の教訓を学び防災対策の見直し拡充を進めることが必要と考えます。
みなさん。政府の地震調査委員会はマグニチュード8~9程度を想定する南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率を「80%程度」に引き上げました。昭和19年(1944年)静岡県など東海地方を襲った「昭和東南海地震」の発生から80年がたち、いつ起きても不思議ではないとされる時期になっています。過去のデータ分析によれば袋井市の震度7だったとされ、多くの建物が倒壊、袋井町では67人が犠牲になったと記録もあります。三川地区でも小学生の犠牲者が出ています。市には災害発生を想定し、しっかりと準備を進めることを求めます。
みなさん。東南海地震が発生すれば、袋井市では沿岸部で津波被害が、平野部では川沿いの低地や沿岸部などに軟弱地盤が多く建物被害が心配されます。東南海地震は被災地が広範囲に及ぶとされ支援の手が届くことが危ぶまれます。圧倒的に支援のマンパワーも不足します。いかに支援が届くまで自助努力でつなぐことができるかが鍵となります。
みなさん。公助に頼るのではなく、自助共助を含め、今からしっかり準備を進めようではありませんか。
2025年01月22日 20:15
日本の食と農を守ろう≫
カテゴリー │袋井市政
「日本の食と農を守ろう」
みなさん。
みなさん。昨年の「令和の米騒動」は日本の食と農の危機の一端を顕在化させました。農業者の減少が加速し、農業と農村は疲弊しています。これは国民の食を外国に依存し農業をつぶしてきた自民党政治の結果です。
昨年の夏場から続いた米不足、収穫の秋になり供給は安定してきましたが、2024年産の取引価格は玄米60キロ2万円超えと、過去最高値となっています。米価上昇の背景となっているコメ不足の最大の原因は米の供給量が少なすぎることです。政府は米の消費量が減少しているとして生産量の削減を求めてきました。しかも米価を市場任せにして農業経営を困難にさせました。主食を安定供給する政府の責任を放棄した結果、供給量が低下し、社会情勢や気候のわずかな変動で価格高騰につながってしまったのです。市場任せの無責任な米政策のもとでは今年も深刻な米不足になりかねません。生活困窮でコメを変えない人が増えています。
みなさん。昨年の米農家の倒産・廃業は過去最多となりました。この原因は。生産コストの上昇と、深刻な後継者不足が原因です。酪農・畜産危機も深刻です。酪農家はこの15年で半減し1万戸を割りました。残った酪農家も6割が赤字で5割近くが離農を検討しているといいます。酪農の灯が消え、新鮮な国産牛乳が飲めなくなりかねません。
しかし、政府には農家の経営を守っていこうという姿勢はまったくありません。多くの国では農家が生産を続けられる価格保障や所得補償を実施しています。
みなさん。気候危機や不安定な世界情勢で、農産物はいつでも輸入できる時代ではありません。食料自給率向上の目標を投げ捨てるような政権に農政をゆだねるわけにはいきません。夏の参院選で自公政権に厳しい審判を下し、食と農の再生に展望を開きましょう。
さて、みなさん。袋井市は太田川周辺に開けた広大な水田、台地にはお茶やミカン、そして暖かな気候・豊かな日射量を活用した温室メロン栽培など、県下でも有数な農業産地です。
しかし、どの作目でも農業従事者が高齢化、後継者不足が顕在化しています「担い手」の確保は喫緊の課題です。袋井市にとって農業は重要な地域産業です。洪水防止のため貯水機能のある水田の保持、豊かな緑・景観を保っていくためにも農業は欠かせない産業です。
国は大規模化や効率化、スマート農業の推進、輸出促進など強調しますがこれでは農村の崩壊は進むばかりです。必要なのは食料自給率を最大の目標に据え、価格保障や所得補償など農家が安心して営農に励める基盤を整えることです。新規参入者を含めて多様な担い手の育成・確保に重点を置くことではないでしょうか。私高橋は現役の農業者として農業の振興に力を尽くしてまいります。
みなさん。
みなさん。昨年の「令和の米騒動」は日本の食と農の危機の一端を顕在化させました。農業者の減少が加速し、農業と農村は疲弊しています。これは国民の食を外国に依存し農業をつぶしてきた自民党政治の結果です。
昨年の夏場から続いた米不足、収穫の秋になり供給は安定してきましたが、2024年産の取引価格は玄米60キロ2万円超えと、過去最高値となっています。米価上昇の背景となっているコメ不足の最大の原因は米の供給量が少なすぎることです。政府は米の消費量が減少しているとして生産量の削減を求めてきました。しかも米価を市場任せにして農業経営を困難にさせました。主食を安定供給する政府の責任を放棄した結果、供給量が低下し、社会情勢や気候のわずかな変動で価格高騰につながってしまったのです。市場任せの無責任な米政策のもとでは今年も深刻な米不足になりかねません。生活困窮でコメを変えない人が増えています。
みなさん。昨年の米農家の倒産・廃業は過去最多となりました。この原因は。生産コストの上昇と、深刻な後継者不足が原因です。酪農・畜産危機も深刻です。酪農家はこの15年で半減し1万戸を割りました。残った酪農家も6割が赤字で5割近くが離農を検討しているといいます。酪農の灯が消え、新鮮な国産牛乳が飲めなくなりかねません。
しかし、政府には農家の経営を守っていこうという姿勢はまったくありません。多くの国では農家が生産を続けられる価格保障や所得補償を実施しています。
みなさん。気候危機や不安定な世界情勢で、農産物はいつでも輸入できる時代ではありません。食料自給率向上の目標を投げ捨てるような政権に農政をゆだねるわけにはいきません。夏の参院選で自公政権に厳しい審判を下し、食と農の再生に展望を開きましょう。
さて、みなさん。袋井市は太田川周辺に開けた広大な水田、台地にはお茶やミカン、そして暖かな気候・豊かな日射量を活用した温室メロン栽培など、県下でも有数な農業産地です。
しかし、どの作目でも農業従事者が高齢化、後継者不足が顕在化しています「担い手」の確保は喫緊の課題です。袋井市にとって農業は重要な地域産業です。洪水防止のため貯水機能のある水田の保持、豊かな緑・景観を保っていくためにも農業は欠かせない産業です。
国は大規模化や効率化、スマート農業の推進、輸出促進など強調しますがこれでは農村の崩壊は進むばかりです。必要なのは食料自給率を最大の目標に据え、価格保障や所得補償など農家が安心して営農に励める基盤を整えることです。新規参入者を含めて多様な担い手の育成・確保に重点を置くことではないでしょうか。私高橋は現役の農業者として農業の振興に力を尽くしてまいります。
2025年01月18日 09:29
高すぎる国保税の引下げを≫
カテゴリー │袋井市政
高すぎる国保税の引下げを
物価高騰が国民の暮らしを直撃する中、自営業者やフリーランス、年金生活者、非正規労働者などが加入する国民健康保険の保険税の値上げが相次ぎ、国民の怒りが広がっています。今年度だけで全国1736自治体のうち、650もの自治体が保険税の値上げを行いました。
今の国保税値上げの背景には政府が2018年度に国保の「都道府県化」を強行したことにあります。市町村が単独で運営してきた国保財政を都道府県と市町村との共同運営に変え、都道府県が値上げの旗振りをしていく仕組みにしました。それまでは国保税の負担抑制のため、多くの市町村が独自に一般会計から国保財政への繰り入れなどの財政措置をしていました。しかし政府は都道府県を通じてこうした独自措置を打ち切るよう圧力をかけてきました。これが国保の大規模な値上げの要因となっているのです。
袋井市でも県が示す統一保険料率に2027年度までに合わせるとして毎年保険料率の改定を行ってきました。2022年から3年かけて資産割を廃止、その分所得割額が値上げされました。世帯比で2023年度は2022年度より19,968円4.4%の引き上げに、2024年度は2023年度より26,656円5.1%の引き上げとなりました。これから3年間は均等割額・平等割額を引き上げる予定で、これからも値上げが続くことになります。
今、生活必需品や資材価格の高騰で、暮らしと営業が厳しさを増しており、「高すぎる国保税」が国民や業者の暮らしを圧迫しています。そんななか、多くの自治体が何らかの形で国保税の減額や実質減額を実施せざるを得ない状況となっています。全国知事会は2014年「低所得者が多く」加入する国保の保険料負担が重いのは『国保の構造問題』だとし、公費1兆円の投入で高すぎる国保税を協会けんぽの保険料並み」に引き下げるよう要望し、その後も要望し続けています。
国保税の値上げは、自営業者や年金生活者、非正規労働者など、国保に加入する人たちの暮らしを圧迫し、とりわけ子育て支援に逆行します。国保加入の2400万人の8%は18歳以下の子供で、子育て世帯に重い保険税負担がのしかかるからです。社会保険や協会けんぽでは子供などの扶養家族が何人いても保険料は変わりません。ところが国保の場合には家族数に応じてかかる「均等割」があるため、子供が多いと国保税が高くなります。
高すぎる国保税引き下げのために、国庫負担の増額で「均等割」をなくすべきではないですか。すでに全国では条例で「高校卒業年齢の18歳以下」の均等割の減免措置を決めた自治体が増えています。袋井市でも実施を求めるとともに、国にこうした措置を求める運動を広げていきましょう。
物価高騰が国民の暮らしを直撃する中、自営業者やフリーランス、年金生活者、非正規労働者などが加入する国民健康保険の保険税の値上げが相次ぎ、国民の怒りが広がっています。今年度だけで全国1736自治体のうち、650もの自治体が保険税の値上げを行いました。
今の国保税値上げの背景には政府が2018年度に国保の「都道府県化」を強行したことにあります。市町村が単独で運営してきた国保財政を都道府県と市町村との共同運営に変え、都道府県が値上げの旗振りをしていく仕組みにしました。それまでは国保税の負担抑制のため、多くの市町村が独自に一般会計から国保財政への繰り入れなどの財政措置をしていました。しかし政府は都道府県を通じてこうした独自措置を打ち切るよう圧力をかけてきました。これが国保の大規模な値上げの要因となっているのです。
袋井市でも県が示す統一保険料率に2027年度までに合わせるとして毎年保険料率の改定を行ってきました。2022年から3年かけて資産割を廃止、その分所得割額が値上げされました。世帯比で2023年度は2022年度より19,968円4.4%の引き上げに、2024年度は2023年度より26,656円5.1%の引き上げとなりました。これから3年間は均等割額・平等割額を引き上げる予定で、これからも値上げが続くことになります。
今、生活必需品や資材価格の高騰で、暮らしと営業が厳しさを増しており、「高すぎる国保税」が国民や業者の暮らしを圧迫しています。そんななか、多くの自治体が何らかの形で国保税の減額や実質減額を実施せざるを得ない状況となっています。全国知事会は2014年「低所得者が多く」加入する国保の保険料負担が重いのは『国保の構造問題』だとし、公費1兆円の投入で高すぎる国保税を協会けんぽの保険料並み」に引き下げるよう要望し、その後も要望し続けています。
国保税の値上げは、自営業者や年金生活者、非正規労働者など、国保に加入する人たちの暮らしを圧迫し、とりわけ子育て支援に逆行します。国保加入の2400万人の8%は18歳以下の子供で、子育て世帯に重い保険税負担がのしかかるからです。社会保険や協会けんぽでは子供などの扶養家族が何人いても保険料は変わりません。ところが国保の場合には家族数に応じてかかる「均等割」があるため、子供が多いと国保税が高くなります。
高すぎる国保税引き下げのために、国庫負担の増額で「均等割」をなくすべきではないですか。すでに全国では条例で「高校卒業年齢の18歳以下」の均等割の減免措置を決めた自治体が増えています。袋井市でも実施を求めるとともに、国にこうした措置を求める運動を広げていきましょう。
2025年01月17日 16:21
学校給食保護者負担金は幼稚園児1食10円月額200円の引き上げに、小学生1食20円月額350円の引き上げに、中学生は1食30円月額600円の引き上げとなります。児童送迎バス料金は6,000円引き上げ年間26,000円となります。初期支援教室自動車借り上げ保護者負担金は週1,000円から1,250円に、放課後児童クラブ保護者負担金は常時利用7,500円が令和8年度から8,200円に、夏休み等の長期休業時もそれぞれ引き上げとなります。さらに来年度から新たに徴収する学習用端末の保証料は月額230円、年間で2,760円の負担増となります。それぞれ物価高騰の影響やそれぞれ理由をあげていますが、保護者にとっては大きな負担増となることに間違いありません。市の試算では年間の負担増の最高は幼稚園で1,900円、小学生で15,670円、で8,620円になるとしています。子どもが2人3人ともなれば数万円もの負担増となります。
憲法26条は「義務教育は、これを無償とする」と規定しています。市も義務教育を無償で行うよう努めるべきです。学校給食費について国は「自治体が施設費と人件費を負担」、「食材費は保護者負担とする」と規定していますが、食育の重要性がさけばれ学校給食が教育の一環となっています。今、全国各地で子育て世帯の負担軽減対策として学校給食の無償化が広がっています。現在、自治体の約4割、全国775の自治体で何らかの形で給食費の無償化を実施しています。自治体の負担を軽減するため、青森県や群馬県、長野県、東京都では助成制度を設けるなどして給食無償化を推進しています。
韓国では現在全国すべての小中高の学校で無償給食が実施されています。インドネシアでも学校給食の無償化プログラムがはじまり徐々に対象が広がっています。日本でもできないはずはありません。日本の国家予算では防衛費が8兆円超となり教育費はその半分の4兆円しかありません。それを逆転させれば給食無償化どころか高校・大学等の高等教育の無償化も実現できます。県内では御前崎市が小中学校の給食無償化を、湖西市でも今年4月から中学校の給食無償化を実施予定となっていて県内でも広がっています。
みなさん。給食無償化は日本共産党が全国各地で市民とともに要求し、運動を進め実現してきました。ぜひ一緒に今度は袋井市でも実現させましょう。
袋井市が学校教育費関連保護者負担の引き上げを計画≫
カテゴリー │袋井市政
袋井市が学校教育費関連の保護者負担の引き上げを計画
袋井市では今年4月から・学校給食費保護者負担金、・児童送迎バス乗車料金・放課後児童クラブ保護者負担金がそれぞれ引き上げられます。それに加え小中学生に配布されている学習用端末(タブレット)に新たに保証料の負担を求めるとしています。学校給食保護者負担金は幼稚園児1食10円月額200円の引き上げに、小学生1食20円月額350円の引き上げに、中学生は1食30円月額600円の引き上げとなります。児童送迎バス料金は6,000円引き上げ年間26,000円となります。初期支援教室自動車借り上げ保護者負担金は週1,000円から1,250円に、放課後児童クラブ保護者負担金は常時利用7,500円が令和8年度から8,200円に、夏休み等の長期休業時もそれぞれ引き上げとなります。さらに来年度から新たに徴収する学習用端末の保証料は月額230円、年間で2,760円の負担増となります。それぞれ物価高騰の影響やそれぞれ理由をあげていますが、保護者にとっては大きな負担増となることに間違いありません。市の試算では年間の負担増の最高は幼稚園で1,900円、小学生で15,670円、で8,620円になるとしています。子どもが2人3人ともなれば数万円もの負担増となります。
憲法26条は「義務教育は、これを無償とする」と規定しています。市も義務教育を無償で行うよう努めるべきです。学校給食費について国は「自治体が施設費と人件費を負担」、「食材費は保護者負担とする」と規定していますが、食育の重要性がさけばれ学校給食が教育の一環となっています。今、全国各地で子育て世帯の負担軽減対策として学校給食の無償化が広がっています。現在、自治体の約4割、全国775の自治体で何らかの形で給食費の無償化を実施しています。自治体の負担を軽減するため、青森県や群馬県、長野県、東京都では助成制度を設けるなどして給食無償化を推進しています。
韓国では現在全国すべての小中高の学校で無償給食が実施されています。インドネシアでも学校給食の無償化プログラムがはじまり徐々に対象が広がっています。日本でもできないはずはありません。日本の国家予算では防衛費が8兆円超となり教育費はその半分の4兆円しかありません。それを逆転させれば給食無償化どころか高校・大学等の高等教育の無償化も実現できます。県内では御前崎市が小中学校の給食無償化を、湖西市でも今年4月から中学校の給食無償化を実施予定となっていて県内でも広がっています。
みなさん。給食無償化は日本共産党が全国各地で市民とともに要求し、運動を進め実現してきました。ぜひ一緒に今度は袋井市でも実現させましょう。
2025年01月13日 20:23
新しい政治実現へ希望の年に≫
カテゴリー
(新しい政治実現へ希望の年に)日本共産党の訴えを紹介します。3
みなさん。情勢の大激動が予想される2025年の幕が明けました。総選挙での国民の審判で、自民公明は少数与党となり、衆議院では数の力で悪法を通せなくなりました。自民党は一部野党の取り込みを企てていますが、自公以外の党がまとまれば国民の利益にかなう法案が通る力関係が生まれています。
みなさん。日本共産党は、この新しい政治プロセスを国民の運動とともにさらに前に進め、切実な願いを実現するために奮闘することをお約束します。
みなさん。自民党ぐるみの裏金事件の真相解明と、裏金づくりの原資となった政治資金パーティー券購入を含む企業・団体献金の全面禁止は政治の大争点です。
自民党は、総選挙で国民の厳しい審判を受けたのに「企業にも献金の権利がある」「禁止より公開が大事だ」などと開き直り、企業・団体献金を廃止させまいと必死に抵抗しています。これは「財界・大企業の利益最優先」「財界の政治窓口」という自民党の本質を示すものではないでしょうか。日本共産党は「選挙権を持たない企業が財力で政治をゆがめることは、国民の参政権を侵害することになる。」と論陣を張り、自民党と全面対決しています。
みなさん。自民党政治で質すべきもう一つのゆがみは、「日米軍事同盟絶対の政治」です。
昨年の臨時国会で与党と国民民主・維新の賛成で成立した補正予算には、能登半島の復旧・復興費の3倍にもなる8千億円超の軍事費が計上されました。昨年末に決まった25年度予算案では、過去最大の8兆7千億円もの軍事費が盛り込まれています。違憲の敵基地攻撃能力の保有などアメリカ言いなりの大軍拡・「戦争国家づくり」の加速が狙われています。
日本共産党は「日米同盟絶対の政治」から抜け出し、憲法9条を生かした外交の力で東アジアに平和をつくる理性ある政治への転換を求めています。
みなさん。暮らしの要求、平和への願いを本格的に実現しようとすれば、財界優先、日米軍事同盟絶対という自民党政治の二つのゆがみとぶつからざるを得ません。衆議院では少数与党となっても参議院では自公が多数を占め「壁」となって立ちふさがります。この「壁」を取り除き、政治をさらに前に進めるカギは、6月に行われる東京都議選、続く7月の参院選で二つのゆがみに切り込む立場を持つ日本共産党を躍進させることです。
みなさん。日本共産党の躍進で「新しい政治のプロセス」を前に進め、自民党政治に代わる新しい政治をともに作り出していこうではありませんか。このことを強く訴えます。
みなさん。情勢の大激動が予想される2025年の幕が明けました。総選挙での国民の審判で、自民公明は少数与党となり、衆議院では数の力で悪法を通せなくなりました。自民党は一部野党の取り込みを企てていますが、自公以外の党がまとまれば国民の利益にかなう法案が通る力関係が生まれています。
みなさん。日本共産党は、この新しい政治プロセスを国民の運動とともにさらに前に進め、切実な願いを実現するために奮闘することをお約束します。
みなさん。自民党ぐるみの裏金事件の真相解明と、裏金づくりの原資となった政治資金パーティー券購入を含む企業・団体献金の全面禁止は政治の大争点です。
自民党は、総選挙で国民の厳しい審判を受けたのに「企業にも献金の権利がある」「禁止より公開が大事だ」などと開き直り、企業・団体献金を廃止させまいと必死に抵抗しています。これは「財界・大企業の利益最優先」「財界の政治窓口」という自民党の本質を示すものではないでしょうか。日本共産党は「選挙権を持たない企業が財力で政治をゆがめることは、国民の参政権を侵害することになる。」と論陣を張り、自民党と全面対決しています。
みなさん。自民党政治で質すべきもう一つのゆがみは、「日米軍事同盟絶対の政治」です。
昨年の臨時国会で与党と国民民主・維新の賛成で成立した補正予算には、能登半島の復旧・復興費の3倍にもなる8千億円超の軍事費が計上されました。昨年末に決まった25年度予算案では、過去最大の8兆7千億円もの軍事費が盛り込まれています。違憲の敵基地攻撃能力の保有などアメリカ言いなりの大軍拡・「戦争国家づくり」の加速が狙われています。
日本共産党は「日米同盟絶対の政治」から抜け出し、憲法9条を生かした外交の力で東アジアに平和をつくる理性ある政治への転換を求めています。
みなさん。暮らしの要求、平和への願いを本格的に実現しようとすれば、財界優先、日米軍事同盟絶対という自民党政治の二つのゆがみとぶつからざるを得ません。衆議院では少数与党となっても参議院では自公が多数を占め「壁」となって立ちふさがります。この「壁」を取り除き、政治をさらに前に進めるカギは、6月に行われる東京都議選、続く7月の参院選で二つのゆがみに切り込む立場を持つ日本共産党を躍進させることです。
みなさん。日本共産党の躍進で「新しい政治のプロセス」を前に進め、自民党政治に代わる新しい政治をともに作り出していこうではありませんか。このことを強く訴えます。
2024年12月14日 19:54
学費値上げを止めるための緊急の予算措置を求めます。≫
カテゴリー │日本共産党
2024年11月27日発表日本共産党の政府への要請文の紹介
みなさん。先の総選挙では主要政党すべてが高等教育の「無償化」「負担軽減」などを公約に掲げ、石破首相も自民党総裁選で「国立大学・高専の無償化」を公約しました。
ところが、9月に東京大学が、学生や大学人の反対の声を押し切って学費値上げを発表しました。東京大学が来年度からの値上げを発表したことで、国立大学での値上げ連鎖が起きかねない状況です。さらに私立大学でもこの間、早稲田大学、慶応大学、明治大学、立命館大学、同志社大学などで値上げが相次ぎ、物価高騰のもとで大幅値上げや学費スライド制の適用など、値上げが加速しています。
みなさん。高すぎる学費が、これ以上値上げされれば、学生も家族も、その負担に耐え切れないことは明らかです。今でさえ、アルバイトと奨学金や教育ローンの謝金なしには大学に通えない学生が多数です。学生、国民の多くが高い学費、重い教育費負担に苦しみ、政治の場ではすべての主要政党が高等教育の「無償化」「負担軽減」を国民に約束しているのに、実際には国立大学でも私立大学でも「学費値上げラッシュ」が起きようとしている、こんなことは異常と言わざるを得ません。みなさん。政治が看過してよいのかが問われています。
みなさん。日本の高等教育予算はOECD(経済協力開発機構)の中でも「最低水準」という状態が長期にわたって続いています。しかも政府は、2004年の国立大学法人化後、1600億円も運営交付金を削減しました。私立大学への私学助成は経常費の1割以下に抑制されたままとなっています。その結果、大学は物価高騰を含め、教育コストの増額などから財政難にあえいでいます。
みなさん。政治によってもたらされた財政難による教育研究費の劣悪化は、日本の大学教育、学術にとって深刻な事態であり、学費値上げの原因となっています。しかし、これを「理由」に「大学の国際競争力強化のため」などと言って、学費値上げを学生と家族に押し付けることは許されません。何よりも問われているのは政治のお責任ではないでしょうか。
みなさん。現状でも、高い学費のもとで「バイト漬けの学生生活」が当たり前のようになり、奨学金という名の借金が、平均でも300万円、大学院に進学すると500万円とも1,000万円とも言われるほど背負わされています。学費値上げを押し付ければ、「大学の国際競争力強化」どころか、逆に、日本の大学教育、学術研究、科学技術の将来は暗澹たるものになってしまいます政治の責任で学費値上げを回避する措置をとるべきです。
みなさん。緊急の手建てには大きな予算は必要ありません。1000億円程度で、国公私立大学、専門学校の来年度の値上げを回避することができます。これは政府がこれまでに削減した国立大学運営交付金1600億円のほんの少しを戻すだけです。
みなさん。学費値上ではなく、高等教育の無償化こそ求められています。日本政府は、2012年に国際人権規約の高等教育無償化条項について留保を撤回し、高等教育を斬新的に無償化することを国民と国際社会に公約しました。しかし、その後、そのための具体的な取り組みは議論もされず、10年以上も「放置」されています。
そもそも憲法は、教育の機会均等を定めており、それを国民に保障するのが政治の責任ではないですか。日本共産党右は、政府に値上げではなく、値下げに向けて踏みだし、高等教育の斬新的無償化を進めることを求めます。
みなさん。先の総選挙では主要政党すべてが高等教育の「無償化」「負担軽減」などを公約に掲げ、石破首相も自民党総裁選で「国立大学・高専の無償化」を公約しました。
ところが、9月に東京大学が、学生や大学人の反対の声を押し切って学費値上げを発表しました。東京大学が来年度からの値上げを発表したことで、国立大学での値上げ連鎖が起きかねない状況です。さらに私立大学でもこの間、早稲田大学、慶応大学、明治大学、立命館大学、同志社大学などで値上げが相次ぎ、物価高騰のもとで大幅値上げや学費スライド制の適用など、値上げが加速しています。
みなさん。高すぎる学費が、これ以上値上げされれば、学生も家族も、その負担に耐え切れないことは明らかです。今でさえ、アルバイトと奨学金や教育ローンの謝金なしには大学に通えない学生が多数です。学生、国民の多くが高い学費、重い教育費負担に苦しみ、政治の場ではすべての主要政党が高等教育の「無償化」「負担軽減」を国民に約束しているのに、実際には国立大学でも私立大学でも「学費値上げラッシュ」が起きようとしている、こんなことは異常と言わざるを得ません。みなさん。政治が看過してよいのかが問われています。
みなさん。日本の高等教育予算はOECD(経済協力開発機構)の中でも「最低水準」という状態が長期にわたって続いています。しかも政府は、2004年の国立大学法人化後、1600億円も運営交付金を削減しました。私立大学への私学助成は経常費の1割以下に抑制されたままとなっています。その結果、大学は物価高騰を含め、教育コストの増額などから財政難にあえいでいます。
みなさん。政治によってもたらされた財政難による教育研究費の劣悪化は、日本の大学教育、学術にとって深刻な事態であり、学費値上げの原因となっています。しかし、これを「理由」に「大学の国際競争力強化のため」などと言って、学費値上げを学生と家族に押し付けることは許されません。何よりも問われているのは政治のお責任ではないでしょうか。
みなさん。現状でも、高い学費のもとで「バイト漬けの学生生活」が当たり前のようになり、奨学金という名の借金が、平均でも300万円、大学院に進学すると500万円とも1,000万円とも言われるほど背負わされています。学費値上げを押し付ければ、「大学の国際競争力強化」どころか、逆に、日本の大学教育、学術研究、科学技術の将来は暗澹たるものになってしまいます政治の責任で学費値上げを回避する措置をとるべきです。
みなさん。緊急の手建てには大きな予算は必要ありません。1000億円程度で、国公私立大学、専門学校の来年度の値上げを回避することができます。これは政府がこれまでに削減した国立大学運営交付金1600億円のほんの少しを戻すだけです。
みなさん。学費値上ではなく、高等教育の無償化こそ求められています。日本政府は、2012年に国際人権規約の高等教育無償化条項について留保を撤回し、高等教育を斬新的に無償化することを国民と国際社会に公約しました。しかし、その後、そのための具体的な取り組みは議論もされず、10年以上も「放置」されています。
そもそも憲法は、教育の機会均等を定めており、それを国民に保障するのが政治の責任ではないですか。日本共産党右は、政府に値上げではなく、値下げに向けて踏みだし、高等教育の斬新的無償化を進めることを求めます。
2024年12月11日 20:00
103万円の壁をどう考えるか。≫
カテゴリー
みなさん。衆議院で自民・公明両党が過半数割れしたもとで「所得税の103万円の壁」が話題となっています。躍進した国民民主党は大学生年代の親の特定扶養控除の年収要件の大幅な緩和求め、この見直しと引き換えに政権与党と経済対策に合意しました。それだけで予算案に賛成にまわるということは事実上の連立政権入りと言えてしまう甘い対応です。
みなさん。年収103万円とは、「所得税の課税最低限」のことです。給与所得者にとっては所得税が課税されない限度額で、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計です。年間の収入が103万円以下なら、この2つの控除を引くと残りがゼロとなってしまうため、所得税が課税されません。しかし、これを超えると、働く本人に所得税がかかり、扶養控除の対象から外れ、扶養者の納税額も増えることになります。それを避けたいパートやアルバイトの働き手による労働時間の調整が人手不足の要因、「壁」と言われてきました。
日本共産党は、課税最低限を引き上げることが必要だとして、総選挙の政策でも主張してきました。日本政府は、憲法25条に基づく生活費非課税の原則を踏みにじり、1995年以来29年間も「103万円の壁」を引き上げてきませんでした。課税最低限が現在の103万円になったのは、1995年ですが、その当時と比べて物価も賃金も10%くらい上がっています。実質の手取りが減らないようにするためには、物価や賃金に合わせて課税最低限を引き上げることが必要です。物価や賃金が上がれば所得税収も自然に増えます。その増収分の一部を還元することで加能井ですから、財源の心配もいりません。
みなさん。国民民主党の案は103万円を178万円に引き上げる(72.8%増)というもので、物価の伸びをはるかに上回る提案です。当然、財源もたくさん必要となり、政府の試算では7.8兆円と言われています。所得税の市自然増収の範囲では全く足りないため、他から財源を持ってくることが必要となります。所得税の減税財源のために教育予算がさらに削られ、大学の授業料が値上げされたら学生にとってもかえってマイナスです。
みなさん。大事なことは衆院の多数を占める野党が結束して与党に迫ることではないでしょうか。「103万円の壁」のほかにも、パートの人にとって問題な「106万円、130万円の保険料の壁」もあります。制度そのものの抜本的見直しが必要です。
みなさん。年収103万円とは、「所得税の課税最低限」のことです。給与所得者にとっては所得税が課税されない限度額で、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計です。年間の収入が103万円以下なら、この2つの控除を引くと残りがゼロとなってしまうため、所得税が課税されません。しかし、これを超えると、働く本人に所得税がかかり、扶養控除の対象から外れ、扶養者の納税額も増えることになります。それを避けたいパートやアルバイトの働き手による労働時間の調整が人手不足の要因、「壁」と言われてきました。
日本共産党は、課税最低限を引き上げることが必要だとして、総選挙の政策でも主張してきました。日本政府は、憲法25条に基づく生活費非課税の原則を踏みにじり、1995年以来29年間も「103万円の壁」を引き上げてきませんでした。課税最低限が現在の103万円になったのは、1995年ですが、その当時と比べて物価も賃金も10%くらい上がっています。実質の手取りが減らないようにするためには、物価や賃金に合わせて課税最低限を引き上げることが必要です。物価や賃金が上がれば所得税収も自然に増えます。その増収分の一部を還元することで加能井ですから、財源の心配もいりません。
みなさん。国民民主党の案は103万円を178万円に引き上げる(72.8%増)というもので、物価の伸びをはるかに上回る提案です。当然、財源もたくさん必要となり、政府の試算では7.8兆円と言われています。所得税の市自然増収の範囲では全く足りないため、他から財源を持ってくることが必要となります。所得税の減税財源のために教育予算がさらに削られ、大学の授業料が値上げされたら学生にとってもかえってマイナスです。
みなさん。大事なことは衆院の多数を占める野党が結束して与党に迫ることではないでしょうか。「103万円の壁」のほかにも、パートの人にとって問題な「106万円、130万円の保険料の壁」もあります。制度そのものの抜本的見直しが必要です。
2024年12月11日 20:00
103万円の壁をどう考えるか。≫
カテゴリー
みなさん。衆議院で自民・公明両党が過半数割れしたもとで「所得税の103万円の壁」が話題となっています。躍進した国民民主党は大学生年代の親の特定扶養控除の年収要件の大幅な緩和求め、この見直しと引き換えに政権与党と経済対策に合意しました。それだけで予算案に賛成にまわるということは事実上の連立政権入りと言えてしまう甘い対応です。
みなさん。年収103万円とは、「所得税の課税最低限」のことです。給与所得者にとっては所得税が課税されない限度額で、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計です。年間の収入が103万円以下なら、この2つの控除を引くと残りがゼロとなってしまうため、所得税が課税されません。しかし、これを超えると、働く本人に所得税がかかり、扶養控除の対象から外れ、扶養者の納税額も増えることになります。それを避けたいパートやアルバイトの働き手による労働時間の調整が人手不足の要因、「壁」と言われてきました。
日本共産党は、課税最低限を引き上げることが必要だとして、総選挙の政策でも主張してきました。日本政府は、憲法25条に基づく生活費非課税の原則を踏みにじり、1995年以来29年間も「103万円の壁」を引き上げてきませんでした。課税最低限が現在の103万円になったのは、1995年ですが、その当時と比べて物価も賃金も10%くらい上がっています。実質の手取りが減らないようにするためには、物価や賃金に合わせて課税最低限を引き上げることが必要です。物価や賃金が上がれば所得税収も自然に増えます。その増収分の一部を還元することで加能井ですから、財源の心配もいりません。
みなさん。国民民主党の案は103万円を178万円に引き上げる(72.8%増)というもので、物価の伸びをはるかに上回る提案です。当然、財源もたくさん必要となり、政府の試算では7.8兆円と言われています。所得税の市自然増収の範囲では全く足りないため、他から財源を持ってくることが必要となります。所得税の減税財源のために教育予算がさらに削られ、大学の授業料が値上げされたら学生にとってもかえってマイナスです。
みなさん。大事なことは衆院の多数を占める野党が結束して与党に迫ることではないでしょうか。「103万円の壁」のほかにも、パートの人にとって問題な「106万円、130万円の保険料の壁」もあります。制度そのものの抜本的見直しが必要です。
みなさん。年収103万円とは、「所得税の課税最低限」のことです。給与所得者にとっては所得税が課税されない限度額で、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計です。年間の収入が103万円以下なら、この2つの控除を引くと残りがゼロとなってしまうため、所得税が課税されません。しかし、これを超えると、働く本人に所得税がかかり、扶養控除の対象から外れ、扶養者の納税額も増えることになります。それを避けたいパートやアルバイトの働き手による労働時間の調整が人手不足の要因、「壁」と言われてきました。
日本共産党は、課税最低限を引き上げることが必要だとして、総選挙の政策でも主張してきました。日本政府は、憲法25条に基づく生活費非課税の原則を踏みにじり、1995年以来29年間も「103万円の壁」を引き上げてきませんでした。課税最低限が現在の103万円になったのは、1995年ですが、その当時と比べて物価も賃金も10%くらい上がっています。実質の手取りが減らないようにするためには、物価や賃金に合わせて課税最低限を引き上げることが必要です。物価や賃金が上がれば所得税収も自然に増えます。その増収分の一部を還元することで加能井ですから、財源の心配もいりません。
みなさん。国民民主党の案は103万円を178万円に引き上げる(72.8%増)というもので、物価の伸びをはるかに上回る提案です。当然、財源もたくさん必要となり、政府の試算では7.8兆円と言われています。所得税の市自然増収の範囲では全く足りないため、他から財源を持ってくることが必要となります。所得税の減税財源のために教育予算がさらに削られ、大学の授業料が値上げされたら学生にとってもかえってマイナスです。
みなさん。大事なことは衆院の多数を占める野党が結束して与党に迫ることではないでしょうか。「103万円の壁」のほかにも、パートの人にとって問題な「106万円、130万円の保険料の壁」もあります。制度そのものの抜本的見直しが必要です。
2024年11月16日 06:03
袋井民主商工会が市に要望書提出・懇談≫
カテゴリー
袋井市が中小企業及び小規模企業振興基本条例を制定、令和7年1月1日から施行
袋井民主商工会は10月8日に市へ要望書を提出。11月14日市からの回答を受け懇談を行いました。
当日は高橋会長、鈴木副会長、町田事務局長が出席。市からは産業未来課の広岡課長、小池係長、水野課職員に対応いただきました。
袋井民商からの要望内容は次の4点です。
①中小企業・小規模企業振興基本条例を制定し、中小企業・小規模企業への支援を行うこと。
②高すぎる国民健康保険税の引き下げを行うこと。均等割は廃止すること。③特に子供の均等割はすぐになくすこと。強権的徴収は行わないこと。
③住宅及び店舗棟リフォーム助成制度を実施すること。
④「物価高騰対策対応っ重点支援地方創生臨時交付金」を活用した施策を検討実施すること。
市からの回答は、3中小企業及び小規模基本条例は9月議会で制定し、令和7年1月1日から施工する。国保税については保険料水準の件統一方針に基づく、標準保険料率とする必要がある。計画的に税率を見直し、標準保険料に近づけていく予定である。均等割については県内すべての市町で設定されていることからないしすることはできない。住宅リフォーム助成事業は令和2年度・令和3年度に実施した。新たな助成制度の実施は国の動向を注視しつつ地域経済の状況を把握し総合的に判断する。物価高騰対応臨時交付金の活用した中小企業向け施策実施については、国の方針に基づく必要な支援を検討していく。というものでした。
そののち、民商側からコロナ期以降需要が回復せず、また物価高騰もあり中小企業の経営が厳しい状況にあること、これまで実施された事業の効果が中小企業まで及んでいない、国保税の負担が重く支払いが困難となっているなど会員の実情が語られました。
袋井民主商工会は10月8日に市へ要望書を提出。11月14日市からの回答を受け懇談を行いました。
当日は高橋会長、鈴木副会長、町田事務局長が出席。市からは産業未来課の広岡課長、小池係長、水野課職員に対応いただきました。
袋井民商からの要望内容は次の4点です。
①中小企業・小規模企業振興基本条例を制定し、中小企業・小規模企業への支援を行うこと。
②高すぎる国民健康保険税の引き下げを行うこと。均等割は廃止すること。③特に子供の均等割はすぐになくすこと。強権的徴収は行わないこと。
③住宅及び店舗棟リフォーム助成制度を実施すること。
④「物価高騰対策対応っ重点支援地方創生臨時交付金」を活用した施策を検討実施すること。
市からの回答は、3中小企業及び小規模基本条例は9月議会で制定し、令和7年1月1日から施工する。国保税については保険料水準の件統一方針に基づく、標準保険料率とする必要がある。計画的に税率を見直し、標準保険料に近づけていく予定である。均等割については県内すべての市町で設定されていることからないしすることはできない。住宅リフォーム助成事業は令和2年度・令和3年度に実施した。新たな助成制度の実施は国の動向を注視しつつ地域経済の状況を把握し総合的に判断する。物価高騰対応臨時交付金の活用した中小企業向け施策実施については、国の方針に基づく必要な支援を検討していく。というものでした。
そののち、民商側からコロナ期以降需要が回復せず、また物価高騰もあり中小企業の経営が厳しい状況にあること、これまで実施された事業の効果が中小企業まで及んでいない、国保税の負担が重く支払いが困難となっているなど会員の実情が語られました。
2024年11月12日 20:58
紙の保険証廃止方針は撤回すべき≫
カテゴリー │国政問題
保険証廃止いまだ混乱
みなさん。自公政権が12月2日に健康保険証の新規発行を停止し、マイナンバーカードと保険証を一体にする「マイナ保険証」の一体化を強行しようとしています。しかし、マイナ保険証をめぐる問題は山積し、現行保険証廃止を掲げた与党は、総選挙で過半数割れを起こしました。数の力でのごり押しは許されません。
みなさん。自公政権が12月2日に健康保険証の新規発行を停止し、マイナンバーカードと保険証を一体にする「マイナ保険証」の一体化を強行しようとしています。しかし、マイナ保険証をめぐる問題は山積し、現行保険証廃止を掲げた与党は、総選挙で過半数割れを起こしました。数の力でのごり押しは許されません。
マイナ保険証の利用は伸びず
みなさん。マイナ保険証の利用率は9月で13.87%。政府が217億円も血税を計上し、医療機関や薬局に「支援金」をばらまき利用促進に駆り立てましたが効果は極めて限定的でした。職責上マイナ保険証を推進する立場の国家公務員の利用率が13.58%と全国平均より低いままです。制度を所管する総務省でも19.42%。厚生労働省でも19.68%。デジタル庁を含む内閣府本府支部は16.06%です。職員が国家機密を扱う防衛省は10.69%、外務省は10.53%です。
みなさん。マイナ保険証の利用率は9月で13.87%。政府が217億円も血税を計上し、医療機関や薬局に「支援金」をばらまき利用促進に駆り立てましたが効果は極めて限定的でした。職責上マイナ保険証を推進する立場の国家公務員の利用率が13.58%と全国平均より低いままです。制度を所管する総務省でも19.42%。厚生労働省でも19.68%。デジタル庁を含む内閣府本府支部は16.06%です。職員が国家機密を扱う防衛省は10.69%、外務省は10.53%です。
相変わらず利用トラブル続出
みなさん。マイナンバーをめぐっては別人の情報が登録されるなどトラブルが多発しました。医療機関ではいまだにトラブルが続いています。全国保険医団体連合会が10月y発表したアンケートでは今年5月以降、約7割の医療機関でマイナ保険証、オンライン資格確認に関するトラブルが発生しています。その対応では「持ち合わせていた保険証で資格確認した」が8割でした。
それでも政府は保険証廃止に固執し、トラブル対策として新たな資格確認方法を追加してきました。その結果、資格確認方法が9種類も存在することになり医療現場の大混乱は必至です。結局、資格確認ができず、患者が10割負担を求められるリスクが高まります。
みなさん。協会けんぽなど被用者保険の加入者にはこの秋、「資格情報のお知らせ」が一斉に送付されました。マイナ保険証を持つ人のトラブルに備えたものですが、マイナ保険証を持たない人も含め全員に送付されています。
みなさん。マイナンバーをめぐっては別人の情報が登録されるなどトラブルが多発しました。医療機関ではいまだにトラブルが続いています。全国保険医団体連合会が10月y発表したアンケートでは今年5月以降、約7割の医療機関でマイナ保険証、オンライン資格確認に関するトラブルが発生しています。その対応では「持ち合わせていた保険証で資格確認した」が8割でした。
それでも政府は保険証廃止に固執し、トラブル対策として新たな資格確認方法を追加してきました。その結果、資格確認方法が9種類も存在することになり医療現場の大混乱は必至です。結局、資格確認ができず、患者が10割負担を求められるリスクが高まります。
みなさん。協会けんぽなど被用者保険の加入者にはこの秋、「資格情報のお知らせ」が一斉に送付されました。マイナ保険証を持つ人のトラブルに備えたものですが、マイナ保険証を持たない人も含め全員に送付されています。
国保加入者にも早期に資格証明書発行の通知をすべき
みなさん。マイナ保険証を持たない人には12月2日以降、申請なしで「資格確認書」が発送されます。それとの違いが分からず、素手日混乱が起きています。最大のトラブル回避策は、現行の保険証の存続です。
いったん立ち止まって、保険証廃止を撤回すべきです。また、10月末からないな保険証を解除できることも周知すべきです。
みなさん。マイナ保険証を持たない人には12月2日以降、申請なしで「資格確認書」が発送されます。それとの違いが分からず、素手日混乱が起きています。最大のトラブル回避策は、現行の保険証の存続です。
いったん立ち止まって、保険証廃止を撤回すべきです。また、10月末からないな保険証を解除できることも周知すべきです。
この記事は11月10日付新聞赤旗日刊紙から引用しました。
2022年01月12日 21:10
今年4月から段階的に国民健康保険税率を改定≫
カテゴリー │袋井市政
今年4月から段階的に国民健康保険税率を改定.県標準保険料率への統一で大幅負担増も
11月5日の市議会全員協議会に県の標準保険料率に合わせるため、令和4年4月から3年かけ段階的に本市の賦課方式を改定する方針が示され、2月議会に保険税改定案が上程される予定です。
賦課方式を改定する理由は
平成30年に国保制度の制度改革が行われ、これまでの市町村単位の運営から都道府県と市町村と共同運営する「県単位運営」に移行しました。
この改革により、県が標準保険料率を毎年示し、市町はそれに基づき国保事業費納付金を収める方式になりました。しかし、現行の本市の賦課方式、保険料率は県の示す賦課方式、保険料率と大きく乖離しており、改定が必要です。(下記表を参照)
国は県単位での国保税の一本化を目指す方向性を示し、県は「令和9年度までに統一を目指す」との方向性を示しています。市は昨年9月の全員協議会に「令和4年4月から資産割の廃止や介護分平等割の廃止など賦課方式の変更を令和4年度から段階的に実施し、令和6年度に完全実施とする。令和4年度の具体的税率は令和3年度に示し協議・決定する。」と提案しており、今回税率が提案となりました。
賦課方式改正に向けた市の方針
令和3年度 現行賦課の最終年度
⇓
令和4~6年度 市が定める方式による賦課
⇓ 6年度から3.3.2方式に
賦課方式を合わせる
令和7~8年度 県が公表する標準保険料率近
⇓ づける
税率を合わせる
令和9年度 県内の標準保険料率一本化
市の現行税率と県公表の本市標準保険税率
諸略
市が予定している保険税率
省略
改正による影響・問題点は
・資産割廃止で所得割が大幅に増加
資産割は現行38.6%が段階的に0%に。その分所得割は現行7.35%が段階的に11.7%となります。資産がない方は減額に、その分所得割が増額に。44%の世帯が減額となり、55%の世帯が増額に。
・国保事業基金で激変緩和措置を実施
まずは賦課方式を変更することに。この間の県の標準料率と税収の差額は「基金」で補てんします。
この為、「基金」は令和3年度末8億7614万円が令和6年度末6億6477万円まで減少。令和7年度からの税率統一でさらに減少し、令和8年度末には枯渇の見通しです。
※ 現行税率のままでは、令和9年度の県納付金は18億67733万円、一方税収は被保険者の減少で15億5064万円との予測です。つまりその差額3億円余の引上げが必要となります。大変な負担増の計画です。一般会計からの繰入はしない、基金がなくなれば補てんもできず、負担増はそのまま被保険者に。低所得者・高齢者が多数を占める国保は全国知事会も提言しているように国による手厚い支援がなければ成り立ちません。
賦課方式を改定する理由は
平成30年に国保制度の制度改革が行われ、これまでの市町村単位の運営から都道府県と市町村と共同運営する「県単位運営」に移行しました。
この改革により、県が標準保険料率を毎年示し、市町はそれに基づき国保事業費納付金を収める方式になりました。しかし、現行の本市の賦課方式、保険料率は県の示す賦課方式、保険料率と大きく乖離しており、改定が必要です。(下記表を参照)
国は県単位での国保税の一本化を目指す方向性を示し、県は「令和9年度までに統一を目指す」との方向性を示しています。市は昨年9月の全員協議会に「令和4年4月から資産割の廃止や介護分平等割の廃止など賦課方式の変更を令和4年度から段階的に実施し、令和6年度に完全実施とする。令和4年度の具体的税率は令和3年度に示し協議・決定する。」と提案しており、今回税率が提案となりました。
賦課方式改正に向けた市の方針
令和3年度 現行賦課の最終年度
⇓
令和4~6年度 市が定める方式による賦課
⇓ 6年度から3.3.2方式に
賦課方式を合わせる
令和7~8年度 県が公表する標準保険料率近
⇓ づける
税率を合わせる
令和9年度 県内の標準保険料率一本化
市の現行税率と県公表の本市標準保険税率
諸略
市が予定している保険税率
省略
改正による影響・問題点は
・資産割廃止で所得割が大幅に増加
資産割は現行38.6%が段階的に0%に。その分所得割は現行7.35%が段階的に11.7%となります。資産がない方は減額に、その分所得割が増額に。44%の世帯が減額となり、55%の世帯が増額に。
・国保事業基金で激変緩和措置を実施
まずは賦課方式を変更することに。この間の県の標準料率と税収の差額は「基金」で補てんします。
この為、「基金」は令和3年度末8億7614万円が令和6年度末6億6477万円まで減少。令和7年度からの税率統一でさらに減少し、令和8年度末には枯渇の見通しです。
※ 現行税率のままでは、令和9年度の県納付金は18億67733万円、一方税収は被保険者の減少で15億5064万円との予測です。つまりその差額3億円余の引上げが必要となります。大変な負担増の計画です。一般会計からの繰入はしない、基金がなくなれば補てんもできず、負担増はそのまま被保険者に。低所得者・高齢者が多数を占める国保は全国知事会も提言しているように国による手厚い支援がなければ成り立ちません。
2022年01月05日 19:08
袋井市スポーツ協会世帯j会費徴収廃止・市予算化≫
カテゴリー │袋井市政
税外負担解消へ一歩
スポーツ協会世帯会費徴収を廃止、市の予算化へ
自治会費にスポーツ協会世帯会費(200円)、社会を明るくする運動会費(50円)、日本赤十字社会費(500円)、社会福祉協議会会費(500円)、赤い羽根共同募金(240円)、歳末助けあい募金(120円)などが加算され(数字は世帯当たりの金額)、袋井市の自治会費が高いとの市民の不満の声、本当に必要か疑問の声が寄せられています。
市は現状確認を実施。他市の状況を調査、関係団体との協議を行い、今後の方針を決定しました。
決定された今後の方針
・袋井市スポーツ協会世帯会費
・社会を明るくする運動会費
⇒令和4年度徴収を廃止、市で予算措置を行う。
・日本赤十字社会費
・袋井市社会福祉協議会会費
・赤い羽根共同募金
・歳末助けあい募金
⇒今後も継続して自治会に協力をお願いする。
スポーツ協会世帯会費徴収を廃止、市の予算化へ
自治会費にスポーツ協会世帯会費(200円)、社会を明るくする運動会費(50円)、日本赤十字社会費(500円)、社会福祉協議会会費(500円)、赤い羽根共同募金(240円)、歳末助けあい募金(120円)などが加算され(数字は世帯当たりの金額)、袋井市の自治会費が高いとの市民の不満の声、本当に必要か疑問の声が寄せられています。
市は現状確認を実施。他市の状況を調査、関係団体との協議を行い、今後の方針を決定しました。
決定された今後の方針
・袋井市スポーツ協会世帯会費
・社会を明るくする運動会費
⇒令和4年度徴収を廃止、市で予算措置を行う。
・日本赤十字社会費
・袋井市社会福祉協議会会費
・赤い羽根共同募金
・歳末助けあい募金
⇒今後も継続して自治会に協力をお願いする。
以上、10月27日開催民生文教委員会の報告の概要です
2022年01月05日 19:00
ゴミ袋有料化見直し、その後の袋井市の方針≫
カテゴリー │袋井市政
ゴミ袋有料化見直し、その後の市の方針
袋井市は11月5日に開かれた市議会全員協議会で、ごみ減量化対策として今年4月からの実施を目指していた「ごみ処理有料化」を見直し、ごみ袋の料金を据え置く方針を明らかにしました。
しかし、12月6日開催の市議会建設経済委員会に報告された方針は、「全体目標は2030年までにごみを30%削減する。2022年4月からの有料化は見合わせ、3年間、市民と共に集中的なごみ減量の取り組みを行い、まずは2024年までに15%の昨年を目指す」とし、「結果、3年間で15%のごみ削減が達成された場合は、ごみ処理手数料の有料化は行わない。ただし、15%の削減目標が達成できなかった場合は、ごみ処理手数料の有料化を実施、同時に記名方式も導入する」「減免についてはその時点で検討する」というものです。
ゴミの削減目標
〇全体(家庭系ごみ及び事業系ごみ)
人口5万人以上の年で最もごみが少ない自治体は本市より30%程度少ない状況であり、本市でも削減は可能であり、30%削減を目標とする。
〇家庭系ごみの削減目標
家庭系ごみを同様に30%削減した場合、全国で4番目に少ない都市となる。削減可能と判断した。
家庭系ごみの削減計画
◎次の施策により、分別・リサイクルを市民と共に徹底し、3年後の目標15%削減を目指す。
〇紙・布類のリサイクル
・新聞紙、段ボール、広告、チラシ
⇒PTAの資源回収、民間の回収ステーションへ
・雑紙(汚れた紙以外)のリサイクル
⇒月2回、各自治会の集団回収で新たに改修実施。
・布のリサイクル
⇒民間の「古紙回収ステーション」に依頼する。
〇プラスチック類
正しい分別補法が分かる動画やチラシによる周知し、可燃ごみに混入されている容器包装プラスチックのリサイクルを推進する。
〇生ごみ
・家庭用生ごみ処理機(コンポストを含む)の普及
⇒補助金を交付し、普及を図る。
・大型生ごみ処理機の共同購入
⇒市が設置し、民間団体に委託、導入実験を行う。
〇草木
⇒市民に八ケ代造園への持ち込みをお願いする。
木の根等、処理料金が高いもののみ中遠クリーンセンターで処理を行う。自治会の希望により、年2回コンテナを設置し回収する。
〇紙おむつ
⇒掛川市、ユニ・チャームと協力し、リサイクルを目指す。
・・・事業系ごみの削減計画、減量化策は割愛。
※ 目標のハードルは高く、達成には市民意識の向上だけでは難しいと思われます。市による市民が利用しやすいシステムや制度の改善が不可欠と考えます。市民負担増ありき、ペナルティを前提では市民の理解はえられません。
袋井市は11月5日に開かれた市議会全員協議会で、ごみ減量化対策として今年4月からの実施を目指していた「ごみ処理有料化」を見直し、ごみ袋の料金を据え置く方針を明らかにしました。
しかし、12月6日開催の市議会建設経済委員会に報告された方針は、「全体目標は2030年までにごみを30%削減する。2022年4月からの有料化は見合わせ、3年間、市民と共に集中的なごみ減量の取り組みを行い、まずは2024年までに15%の昨年を目指す」とし、「結果、3年間で15%のごみ削減が達成された場合は、ごみ処理手数料の有料化は行わない。ただし、15%の削減目標が達成できなかった場合は、ごみ処理手数料の有料化を実施、同時に記名方式も導入する」「減免についてはその時点で検討する」というものです。
ゴミの削減目標
〇全体(家庭系ごみ及び事業系ごみ)
人口5万人以上の年で最もごみが少ない自治体は本市より30%程度少ない状況であり、本市でも削減は可能であり、30%削減を目標とする。
〇家庭系ごみの削減目標
家庭系ごみを同様に30%削減した場合、全国で4番目に少ない都市となる。削減可能と判断した。
家庭系ごみの削減計画
◎次の施策により、分別・リサイクルを市民と共に徹底し、3年後の目標15%削減を目指す。
〇紙・布類のリサイクル
・新聞紙、段ボール、広告、チラシ
⇒PTAの資源回収、民間の回収ステーションへ
・雑紙(汚れた紙以外)のリサイクル
⇒月2回、各自治会の集団回収で新たに改修実施。
・布のリサイクル
⇒民間の「古紙回収ステーション」に依頼する。
〇プラスチック類
正しい分別補法が分かる動画やチラシによる周知し、可燃ごみに混入されている容器包装プラスチックのリサイクルを推進する。
〇生ごみ
・家庭用生ごみ処理機(コンポストを含む)の普及
⇒補助金を交付し、普及を図る。
・大型生ごみ処理機の共同購入
⇒市が設置し、民間団体に委託、導入実験を行う。
〇草木
⇒市民に八ケ代造園への持ち込みをお願いする。
木の根等、処理料金が高いもののみ中遠クリーンセンターで処理を行う。自治会の希望により、年2回コンテナを設置し回収する。
〇紙おむつ
⇒掛川市、ユニ・チャームと協力し、リサイクルを目指す。
・・・事業系ごみの削減計画、減量化策は割愛。
※ 目標のハードルは高く、達成には市民意識の向上だけでは難しいと思われます。市による市民が利用しやすいシステムや制度の改善が不可欠と考えます。市民負担増ありき、ペナルティを前提では市民の理解はえられません。
2021年10月10日 19:26
水道料金・下水道使用料引上げ決定≫
カテゴリー │議会活動
9月議会で水道料金・下水道使用料の引上げ条例を可決
袋井市では概ね5年ごとに水道料金、下水道料金の適正化を図るためとして有識者の「懇話会」を設置、協議を実施し、市長に意見書の提出。それを受け市は、料金改正を実施してきました。
今回の引上げについては、令和3年3月に料金・使用料改定が必要との「意見書」提出されています。市はそれを受け、当初は令和3年4月からの改定を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の流行による市民生活への影響を考慮し、一旦は改定を見送ってきました。
しかし、今回の9月定例会に来年4月からの改定を行うとした条例改正案を上程し、賛成多数で可決となりました。日本共産党の竹村眞弓議員は反対し、討論を行いました。
水道料金の改正案の内容
◎改正の理由
水道事業は、非常時でも水道水を安全かつ安定的に供給するために、災害に強い水道施設への更新を計画的に推進する必要がある。
◎平均改定率11.4%
(前回改定 平成28年度平均改定率 4.2%)
・モデルケース(一般家庭)の場合
口径13mm、2カ月分、使用水量40㎥で算定
現行料金 5,253円(消費税込み)
新料金案 5,940円(消費税込み)
2カ月で687円の増となる。
◎改定時期
令和4年4月1日から
◎料金改定の必要性
・人口減少や節水機器の普及に伴い水需要の減少が見込まれる中、水の安定供給が持続できる料金体系への見直しが必要である。
・大規模災害に備えた水道施設の耐震化や老朽化にともなう更新を計画的に行うには、現状より毎年1.8億円の費用が必要となる。
・更新費用の削減や企業債の増額を検討し、目標収入額を算定した結果、必要となる料金収入額を確保するためには、料金改定が必要となる。
下水道使用料の改正案の内容
◎改正の理由
下水道事業は、事業の計画的な推進や維持管理コストの抑制、公営企業としての経営改善の取り組みなどに加え、国の方針で示される使用料単価に対して不足が生じている。その不足分は、一般会計からの繰入金により補てんしている状況であり、改善が求められる。
◎平均改定率20.0%
(前回改定 平成28年度平均改定率 12%)
・モデルケース(一般家庭)の場合
2カ月分 使用水量40㎥で算定
現行使用料 4,039円(消費税込み)
新使用料案 4,875円(消費税込み)
2カ月で836円の増となる。
◎改定時期
令和4年4月1日から
◎料金改定の必要性
・使用料単価は、公共下水道事業104円/㎥(平成30年度時点)、農業集落排水事業102円/㎥となっており、国が示す単価150円/㎥とは大きく乖離している。
・下水道事業への一般会計からの繰入金は、令和3年度予算では約9億3750万円で、受益者以外の負担となっている。
・下水道事業は公営企業として独立採算制が前提であり、経営の健全化や市民負担の適正化を図ることが必要。
※私の見解
市として経営の健全性を保つ責任は認めるものですが、その負担をそのまま市民にかぶせていいのか疑問です。現在コロナ禍で景気が低迷、市民の収入が減少し市民生活が厳しい今、負担を被せるべきではありません。
水道事業は利用予測を過大に見誤り、ダウンサイジングが必要となっています。下水道事業も当初から採算性に疑問があり、計画どおりの推進には無理があり、推進地域を見直し縮小しました。
しかし、それらの負担の付けは将来にわたって利用者、市民に及ぶことになります。
今後も度々同様の料金・使用料改定が実施される見込みです。利用者負担引上げの悪循環の解消を図る方策を探るべきです。
ごみ袋有料化反対署名に取組んでいます。
市は来年4月からごみ袋代にゴミ処理料金1ℓ1円を上乗せする有料化を実施するとして説明会を実施。しかし市民の理解は得られていません。有料化の見直しを求め、署名に取組んでいます。皆さんの協力をお願いします。
袋井市では概ね5年ごとに水道料金、下水道料金の適正化を図るためとして有識者の「懇話会」を設置、協議を実施し、市長に意見書の提出。それを受け市は、料金改正を実施してきました。
今回の引上げについては、令和3年3月に料金・使用料改定が必要との「意見書」提出されています。市はそれを受け、当初は令和3年4月からの改定を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の流行による市民生活への影響を考慮し、一旦は改定を見送ってきました。
しかし、今回の9月定例会に来年4月からの改定を行うとした条例改正案を上程し、賛成多数で可決となりました。日本共産党の竹村眞弓議員は反対し、討論を行いました。
水道料金の改正案の内容
◎改正の理由
水道事業は、非常時でも水道水を安全かつ安定的に供給するために、災害に強い水道施設への更新を計画的に推進する必要がある。
◎平均改定率11.4%
(前回改定 平成28年度平均改定率 4.2%)
・モデルケース(一般家庭)の場合
口径13mm、2カ月分、使用水量40㎥で算定
現行料金 5,253円(消費税込み)
新料金案 5,940円(消費税込み)
2カ月で687円の増となる。
◎改定時期
令和4年4月1日から
◎料金改定の必要性
・人口減少や節水機器の普及に伴い水需要の減少が見込まれる中、水の安定供給が持続できる料金体系への見直しが必要である。
・大規模災害に備えた水道施設の耐震化や老朽化にともなう更新を計画的に行うには、現状より毎年1.8億円の費用が必要となる。
・更新費用の削減や企業債の増額を検討し、目標収入額を算定した結果、必要となる料金収入額を確保するためには、料金改定が必要となる。
下水道使用料の改正案の内容
◎改正の理由
下水道事業は、事業の計画的な推進や維持管理コストの抑制、公営企業としての経営改善の取り組みなどに加え、国の方針で示される使用料単価に対して不足が生じている。その不足分は、一般会計からの繰入金により補てんしている状況であり、改善が求められる。
◎平均改定率20.0%
(前回改定 平成28年度平均改定率 12%)
・モデルケース(一般家庭)の場合
2カ月分 使用水量40㎥で算定
現行使用料 4,039円(消費税込み)
新使用料案 4,875円(消費税込み)
2カ月で836円の増となる。
◎改定時期
令和4年4月1日から
◎料金改定の必要性
・使用料単価は、公共下水道事業104円/㎥(平成30年度時点)、農業集落排水事業102円/㎥となっており、国が示す単価150円/㎥とは大きく乖離している。
・下水道事業への一般会計からの繰入金は、令和3年度予算では約9億3750万円で、受益者以外の負担となっている。
・下水道事業は公営企業として独立採算制が前提であり、経営の健全化や市民負担の適正化を図ることが必要。
※私の見解
市として経営の健全性を保つ責任は認めるものですが、その負担をそのまま市民にかぶせていいのか疑問です。現在コロナ禍で景気が低迷、市民の収入が減少し市民生活が厳しい今、負担を被せるべきではありません。
水道事業は利用予測を過大に見誤り、ダウンサイジングが必要となっています。下水道事業も当初から採算性に疑問があり、計画どおりの推進には無理があり、推進地域を見直し縮小しました。
しかし、それらの負担の付けは将来にわたって利用者、市民に及ぶことになります。
今後も度々同様の料金・使用料改定が実施される見込みです。利用者負担引上げの悪循環の解消を図る方策を探るべきです。
ごみ袋有料化反対署名に取組んでいます。
市は来年4月からごみ袋代にゴミ処理料金1ℓ1円を上乗せする有料化を実施するとして説明会を実施。しかし市民の理解は得られていません。有料化の見直しを求め、署名に取組んでいます。皆さんの協力をお願いします。
2021年06月13日 04:59
袋井市議会6月定例会一般質問の順番決まる≫
カテゴリー │議会活動
2021年6月議会一般質問日程
6月15日(火)
午前 竹村眞弓議員 竹野 昇議員
午後 大庭通嘉議員 近藤正美議員 安間 亨議員
6月16日(水)
午前 寺田 守議員 鈴木賢和議員 村松和幸議員
午後 山田貴子議員 鈴木弘睦議員 村井勝彦議員
6月17日(木)
午前 立石康弘議員 木下 正議員 太田裕介議員
※ 今回の通告者は14人であり、改選後の初議会であり多くの質問者があることを歓迎します。一般質問実施は議員の権利でもあり、責務でもあります。 私は現職の時には欠かさず取り組んできました。
私は常々新人議員は1期の間、毎回取り組むべきでありそれが勉強になると言い続けてきました。新人議員、元職議員が取り組まないことは何なのでしょうか。立候補した真意が問われます。
袋井市議会では慣例として正副議長、監査委員は行わないとしていますが、今回は監査委員の大庭議員も取り組みます。新市長が誕生し、その市長の政治姿勢を明らかにすること議員にとって重要な責務と考えます。
6月15日(火)
午前 竹村眞弓議員 竹野 昇議員
午後 大庭通嘉議員 近藤正美議員 安間 亨議員
6月16日(水)
午前 寺田 守議員 鈴木賢和議員 村松和幸議員
午後 山田貴子議員 鈴木弘睦議員 村井勝彦議員
6月17日(木)
午前 立石康弘議員 木下 正議員 太田裕介議員
※ 今回の通告者は14人であり、改選後の初議会であり多くの質問者があることを歓迎します。一般質問実施は議員の権利でもあり、責務でもあります。 私は現職の時には欠かさず取り組んできました。
私は常々新人議員は1期の間、毎回取り組むべきでありそれが勉強になると言い続けてきました。新人議員、元職議員が取り組まないことは何なのでしょうか。立候補した真意が問われます。
袋井市議会では慣例として正副議長、監査委員は行わないとしていますが、今回は監査委員の大庭議員も取り組みます。新市長が誕生し、その市長の政治姿勢を明らかにすること議員にとって重要な責務と考えます。
2021年06月10日 05:10
大場規之新袋井市長の所信表明に違和感≫
カテゴリー │議会活動
6月市議会定例会初日の6月7日、大場規之新袋井市長の所信表明を行いました。原田前市長が進めてきた「日本一健康文化都市」実現の取り組みを継承するとし、「全ての人々が幸せで笑顔でいられる街であることを実感できるよう、全身全霊で取り組んでいく」と述べました。
主要取り組み項目に、産業・経済、子育て・教育、健康・福祉、安全・安心、文化・スポーツ、市役所機能の6つの項目をあげ、それぞれにスマイル!の冠を付けているが意味が伝わらず疑問。
大場市長は選挙選で「スマイルシティふくろい」を呼びかけました。「笑顔」には幸せを感じた際にそれを周囲と共有する力だけでなく、困難な時に心に余裕を生み、前を向いて歩みを進める力がある。市民一人一人が安心して将来に希望をもって、日々暮らすことができているかどうかの一つのバロメーターが笑顔であるとの説明もありました。 しかし、「スマイル」という言葉がが市民にそうした認識を持って受け入れられるか疑問に感じます。
所要項目の取り組み内容が具体性に乏しすぎる。
産業・経済では、市長によるトップセールス、「ふくろい産業イノベーションセンター」における中小企業支援、農業ではICTを活用した生産性向上、観光資源として新たに「海」の活用など。 教育・子育てではICTを活用した教育の推進と、保育需要高まりへの対応など。健康・福祉では、健康寿命日本一を目指しまずは健康寿命県内1位を目指して取り組む。安全・安心では、地域防災訓練を実践的で効果の高い訓練を実施するなど。文化・スポーツでは、中学校の休日部活動の段階的な地域移行に向けての外部指導員の確保など。市役所機能では、浅羽支所の利活用など。それぞれ取り上げておりますが、ICTへの過度な期待やそのどれも説明が不十分であり具体策に乏しくその実現が危ぶまれます。
大場市長が現場をしっかり把握しより具体的な提案発言をすることを望みます。
主要取り組み項目に、産業・経済、子育て・教育、健康・福祉、安全・安心、文化・スポーツ、市役所機能の6つの項目をあげ、それぞれにスマイル!の冠を付けているが意味が伝わらず疑問。
大場市長は選挙選で「スマイルシティふくろい」を呼びかけました。「笑顔」には幸せを感じた際にそれを周囲と共有する力だけでなく、困難な時に心に余裕を生み、前を向いて歩みを進める力がある。市民一人一人が安心して将来に希望をもって、日々暮らすことができているかどうかの一つのバロメーターが笑顔であるとの説明もありました。 しかし、「スマイル」という言葉がが市民にそうした認識を持って受け入れられるか疑問に感じます。
所要項目の取り組み内容が具体性に乏しすぎる。
産業・経済では、市長によるトップセールス、「ふくろい産業イノベーションセンター」における中小企業支援、農業ではICTを活用した生産性向上、観光資源として新たに「海」の活用など。 教育・子育てではICTを活用した教育の推進と、保育需要高まりへの対応など。健康・福祉では、健康寿命日本一を目指しまずは健康寿命県内1位を目指して取り組む。安全・安心では、地域防災訓練を実践的で効果の高い訓練を実施するなど。文化・スポーツでは、中学校の休日部活動の段階的な地域移行に向けての外部指導員の確保など。市役所機能では、浅羽支所の利活用など。それぞれ取り上げておりますが、ICTへの過度な期待やそのどれも説明が不十分であり具体策に乏しくその実現が危ぶまれます。
大場市長が現場をしっかり把握しより具体的な提案発言をすることを望みます。
2021年06月09日 04:54
新型コロナワクチン接種のためのタクシー利用に助成金実現≫
カテゴリー │議会活動
高齢者や障がい者等の生活弱者がコロナワクチン接種会場までの交通手段がないことが問題となっていて、袋井生活と健康を守る会は袋井市にタクシー料金の助成をするようを申し入れを行っております。また、日本共産党の竹村眞弓議員も一般質問の通告をしておりました。
袋井市は6月7日、市内に住む交通手段のない65歳以上の高齢者や障がい者に対し、自宅から新型コロナウイルスワクチン接種場所までの往復のタクシー運賃の一部を助成する事業を始めたと発表しました。期間は2022年3月末までです。この決定を歓迎するとともに、こうした関係者の声に耳を傾けもっと早期に決定すべきでした。
市の助成制度の概要は次の通りです。
市が指定する袋井交通・袋井卓志^の2社を利用して自宅から接種場所、または接種場所から自宅に移動するなどした際、1乗車につき600円を上限に補助する。2回の接種では最大2,400円が助成される。運賃が600円を超えた分は自己負担となる。
利用者はタクシー車内にある申請書に氏名を記入して運転手に提出。接種券を提示し、600円を差し引いた運賃を支払う。
対象は、⓵65歳以上で接種場所までの移動社団のない人②身体障碍者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を所持している人➂要支援・要介護認定を受けている人。
市は750人程の利用を見込んでおります。詳しい内容は市協働まちづくり課に問合せ下さい。
袋井市は6月7日、市内に住む交通手段のない65歳以上の高齢者や障がい者に対し、自宅から新型コロナウイルスワクチン接種場所までの往復のタクシー運賃の一部を助成する事業を始めたと発表しました。期間は2022年3月末までです。この決定を歓迎するとともに、こうした関係者の声に耳を傾けもっと早期に決定すべきでした。
市の助成制度の概要は次の通りです。
市が指定する袋井交通・袋井卓志^の2社を利用して自宅から接種場所、または接種場所から自宅に移動するなどした際、1乗車につき600円を上限に補助する。2回の接種では最大2,400円が助成される。運賃が600円を超えた分は自己負担となる。
利用者はタクシー車内にある申請書に氏名を記入して運転手に提出。接種券を提示し、600円を差し引いた運賃を支払う。
対象は、⓵65歳以上で接種場所までの移動社団のない人②身体障碍者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を所持している人➂要支援・要介護認定を受けている人。
市は750人程の利用を見込んでおります。詳しい内容は市協働まちづくり課に問合せ下さい。
2021年03月30日 05:24
袋井市の新型コロナウイルスワクチン接種計画≫
カテゴリー │議会活動
新型コロナウイルスワクチン接種
医療従事者は4月下旬、高齢者は5月上旬開始予定
※国のワクチンの確保が遅れ、その供給も見通しも不明確であり、市も対応に苦慮しています。あくまで現時点(3月22日全員協議会報告)での計画であり、変更も予想されます。
袋井市におけるワクチン接種
国の指針、県の方針に基づき、ワクチンの供給状況に合わせて順次実施していきます。まずは医療従事者への接種を4月下旬に開始し、次に65歳以上の高齢者への接種を開始します。64歳以下の方については、ワクチンの供給状況に合わせて、順次接種していきます。
新型コロナウイルスワクチンの配分見通し
国から県に出荷された後、県から各市町に配分されます。現時点において、医療従事者分は5月前半までに、高齢者分は6月末までに、対象者全員の接種に必要な量が各市町に配分される見込みです。
ワクチン接種についての袋井市の方針
医療従事者等
4月から接種を開始し、5月末までに対象者全員の接種完了を目指す。接種方法は、接種後の体調の変化を考慮し、集団接種及び個別接種により分散して接種する。
・医師会約620人・歯科医師会、薬剤師会、救急隊員等約680人。接種会場は、⓵総合健康センター②さわやかアリーナ➂聖隷袋井市民病院。日程は、⓵②は土・日曜日、➂は平日の午後。方法は、⓵②は集団接種、③は聖隷袋井市民病院での接種。
65歳以上の高齢者
5月上旬から接種を開始し、7月末までに高齢者全員への接種完了を目指す。接種券発送については、予約受付の混雑を回避するため、年代別により段階的に発送する。
接種方法―集団接種、個別接種及び巡回接種都市、約3カ月間で一人2回の接種を実施する。
接種券の発送時期―4月中旬以降になる。接種券が届いてからの予約となる。予約には接種券番号と生年月日が必要です。
集団接種の会場―さわやかアリーナ
聖隷袋井市民病院
浅羽支所又は浅羽保健センター
・市内の65歳以上の高齢者約23,000人
一般の高齢者約15,000人(接種率70%で算定)
接種会場は、⓵さわやかアリーナ②浅羽支所または浅羽保健センター➂聖隷袋井市民病院④市内の医療機関。日程は、⓵日曜日②水曜日➂平日の午後④医療機関の開業時間。方法は、⓵②集団接種、➂聖隷袋井市民病院での接種。④市内の医療機関での接種(医師会と協議中)
高齢者施設入所者約1300人施設従事者約700人
接種会場は各高齢者施設、日程は高齢者施設と調整して実施。方法は、サテライト型接種または巡回接種。
・市内の医療機関での個別接種
市内で接種することができる医療機関については、現在調整中です。
・ワクチン接種の予約と相談
市が実施する集団接種の予約は、インターネットの他、市ワクチン接種コールセンターでの電話予約を受け付けます。5月頃からは、高齢者が定期的に集まる健康教室やコミュニティセンターを巡回し予約受付を行います。
袋井市ワクチン接種コールセンターの開設
市民からの問い合わせや、インターネット予約が難しい高齢者等の方の電話予約に対応します。接種券発送後は、当分の間、平日だけでなく土日祝日も対応し、市民の不安解消に努めます。
電話番号 0538-84-7813
開設日 令和3年3月15日(月)
受付期間 午前9時から午後5時まで
・ワクチンの副反応に関する相談
静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口で受け付けています。
☎050-5445-2369
64歳以下の接種
国から、配分時期が示されてさおらず、現時点では未定です。高齢者の接種完了後となります。
医療従事者は4月下旬、高齢者は5月上旬開始予定
※国のワクチンの確保が遅れ、その供給も見通しも不明確であり、市も対応に苦慮しています。あくまで現時点(3月22日全員協議会報告)での計画であり、変更も予想されます。
袋井市におけるワクチン接種
国の指針、県の方針に基づき、ワクチンの供給状況に合わせて順次実施していきます。まずは医療従事者への接種を4月下旬に開始し、次に65歳以上の高齢者への接種を開始します。64歳以下の方については、ワクチンの供給状況に合わせて、順次接種していきます。
新型コロナウイルスワクチンの配分見通し
国から県に出荷された後、県から各市町に配分されます。現時点において、医療従事者分は5月前半までに、高齢者分は6月末までに、対象者全員の接種に必要な量が各市町に配分される見込みです。
ワクチン接種についての袋井市の方針
医療従事者等
4月から接種を開始し、5月末までに対象者全員の接種完了を目指す。接種方法は、接種後の体調の変化を考慮し、集団接種及び個別接種により分散して接種する。
・医師会約620人・歯科医師会、薬剤師会、救急隊員等約680人。接種会場は、⓵総合健康センター②さわやかアリーナ➂聖隷袋井市民病院。日程は、⓵②は土・日曜日、➂は平日の午後。方法は、⓵②は集団接種、③は聖隷袋井市民病院での接種。
65歳以上の高齢者
5月上旬から接種を開始し、7月末までに高齢者全員への接種完了を目指す。接種券発送については、予約受付の混雑を回避するため、年代別により段階的に発送する。
接種方法―集団接種、個別接種及び巡回接種都市、約3カ月間で一人2回の接種を実施する。
接種券の発送時期―4月中旬以降になる。接種券が届いてからの予約となる。予約には接種券番号と生年月日が必要です。
集団接種の会場―さわやかアリーナ
聖隷袋井市民病院
浅羽支所又は浅羽保健センター
・市内の65歳以上の高齢者約23,000人
一般の高齢者約15,000人(接種率70%で算定)
接種会場は、⓵さわやかアリーナ②浅羽支所または浅羽保健センター➂聖隷袋井市民病院④市内の医療機関。日程は、⓵日曜日②水曜日➂平日の午後④医療機関の開業時間。方法は、⓵②集団接種、➂聖隷袋井市民病院での接種。④市内の医療機関での接種(医師会と協議中)
高齢者施設入所者約1300人施設従事者約700人
接種会場は各高齢者施設、日程は高齢者施設と調整して実施。方法は、サテライト型接種または巡回接種。
・市内の医療機関での個別接種
市内で接種することができる医療機関については、現在調整中です。
・ワクチン接種の予約と相談
市が実施する集団接種の予約は、インターネットの他、市ワクチン接種コールセンターでの電話予約を受け付けます。5月頃からは、高齢者が定期的に集まる健康教室やコミュニティセンターを巡回し予約受付を行います。
袋井市ワクチン接種コールセンターの開設
市民からの問い合わせや、インターネット予約が難しい高齢者等の方の電話予約に対応します。接種券発送後は、当分の間、平日だけでなく土日祝日も対応し、市民の不安解消に努めます。
電話番号 0538-84-7813
開設日 令和3年3月15日(月)
受付期間 午前9時から午後5時まで
・ワクチンの副反応に関する相談
静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口で受け付けています。
☎050-5445-2369
64歳以下の接種
国から、配分時期が示されてさおらず、現時点では未定です。高齢者の接種完了後となります。