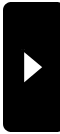2018年01月09日19:44
就学前の子どもの教育・保育のあり方に関する基本方針(案)≫
カテゴリー │議会活動
12月21日開催,全員協議会報告
就学前の子どもの教育・保育のあり方に関する基本方針(案)
袋井市ではこれまで、公立・私立の幼稚園、保育所、認定子ども園という多様な選択肢があり、保護者ニーズの応じて選ぶことができる環境を整えてきました。中でも公立幼稚園は、各地区に概ね1施設ずつ整備され、地域や小学校等と連携しやすいことが大きな特色である。
昨今、幼稚園の定員割れ、保育所の待機児童、公立幼稚園及び保育所施設の老朽化が課題となっている。
本年度、市は「袋井市の就学前の子どもの教育・保育の在り方検討会」を設置し、概ね10年間を見据えた基本方針を策定した。
袋井市における就学前の教育・保育のねらい
幼児にとって安心できる小学校への接続となるよう、アプローチカリキュラム、スタートカリキュラムを作成し実践していくうえで、現在も実施している幼稚園と小学校の教員、幼児と児童の交流、園運営への地域の協力体制を生かし、公立幼稚園が保幼小接続の基準的役割を担い、幼稚園、保育所等と小学校の一貫した教育を推進していく。保幼小を接続することにより、学力向上の効果や不登校対策に繋げるとともに、就学前の教育・保育全体の質を高め、「新しい環境に適応する力」を子供に育み、幼小中一貫教育において目指す子ども像である「夢を抱き、たくましく次の一歩を踏み出す15歳」を育成する第一歩としていく。
就学前の教育・保育の質の向上と公立保育園の役割
・保幼小接続の基準的な役割を担う
小学校との連携のしやすさが最大の利点
・幼児期の教育の研修や実践の基準的な役割を担う
研修や実践の成果を私立の幼稚園、保育所、小学校等に発信していく役割
・特別支援教育の先導的な役割を担う
平成14年度から拠点園方式で重度の自閉児や肢体不自由児の受け入れ開始、平成21年度から支援を必要とする幼稚園に支援員配置、平成22年度から障がいの状況に応じて必要な支援員を配置、平成23年度から外国人通訳支援員を配置し巡回
・教育・保育施設の運営について
行政が基準的な役割を担い、市内の公立・私立の教育・保育施設が共通の理解をする中で連携・協力し、幼児期の教育全体の充実を図っていく。
袋井市立幼稚園の適正規模、適正配置について
・袋井市立幼稚園における1学級の適正人数
3歳児が20人程度、4歳児が30人程度、5歳児が30人程度と設定する。1学級の最低人数は、集団生活を通じて「生きる力」の基礎を養うため、経営意識を持った幼稚園運営の観点から、10人を下回ることのないよう保護者ニーズに応じた工夫や努力をする。
・袋井市立幼稚園における適正な学級数
幼児教育においては、より多くの幼児と出会い、多様な関係を構築することによって経験が積めることから、1学年の学級数は複数が望ましい。
・袋井市立幼稚園における統廃合の考え方
今後概ね10年間は1小学校区につき1公立園を存続させていくことが望ましいが、社会情勢や保護者ニーズの動向、幼児期における教育環境の適正規模、財政的状況などの諸条件を見極めながら総合的に判断し、状況の変化に柔軟な対応も必要。
・幼保一元化(認定こども園化)の推進
公立保育所は近隣幼稚園との統合による認定子ども園化を検討する。中学校区を1つの単位として圏域に設定、将来的には圏域内における公立又は私立の認定子ども園の必要性について検討する。
まとめ
殊更に直近の保育定員の量的拡大のみに特化した待機児童対策や、拙速な公立施設の統廃合の判断などにより、子どもたちの育ちの環境や教育・保育の質を低下させることのないよう、基本方針の内容を今後の事業計画に反映させ、本市の地域の特性に応じた子育て支援施策を推進していく。
就学前の子どもの教育・保育のあり方に関する基本方針(案)
袋井市ではこれまで、公立・私立の幼稚園、保育所、認定子ども園という多様な選択肢があり、保護者ニーズの応じて選ぶことができる環境を整えてきました。中でも公立幼稚園は、各地区に概ね1施設ずつ整備され、地域や小学校等と連携しやすいことが大きな特色である。
昨今、幼稚園の定員割れ、保育所の待機児童、公立幼稚園及び保育所施設の老朽化が課題となっている。
本年度、市は「袋井市の就学前の子どもの教育・保育の在り方検討会」を設置し、概ね10年間を見据えた基本方針を策定した。
袋井市における就学前の教育・保育のねらい
幼児にとって安心できる小学校への接続となるよう、アプローチカリキュラム、スタートカリキュラムを作成し実践していくうえで、現在も実施している幼稚園と小学校の教員、幼児と児童の交流、園運営への地域の協力体制を生かし、公立幼稚園が保幼小接続の基準的役割を担い、幼稚園、保育所等と小学校の一貫した教育を推進していく。保幼小を接続することにより、学力向上の効果や不登校対策に繋げるとともに、就学前の教育・保育全体の質を高め、「新しい環境に適応する力」を子供に育み、幼小中一貫教育において目指す子ども像である「夢を抱き、たくましく次の一歩を踏み出す15歳」を育成する第一歩としていく。
就学前の教育・保育の質の向上と公立保育園の役割
・保幼小接続の基準的な役割を担う
小学校との連携のしやすさが最大の利点
・幼児期の教育の研修や実践の基準的な役割を担う
研修や実践の成果を私立の幼稚園、保育所、小学校等に発信していく役割
・特別支援教育の先導的な役割を担う
平成14年度から拠点園方式で重度の自閉児や肢体不自由児の受け入れ開始、平成21年度から支援を必要とする幼稚園に支援員配置、平成22年度から障がいの状況に応じて必要な支援員を配置、平成23年度から外国人通訳支援員を配置し巡回
・教育・保育施設の運営について
行政が基準的な役割を担い、市内の公立・私立の教育・保育施設が共通の理解をする中で連携・協力し、幼児期の教育全体の充実を図っていく。
袋井市立幼稚園の適正規模、適正配置について
・袋井市立幼稚園における1学級の適正人数
3歳児が20人程度、4歳児が30人程度、5歳児が30人程度と設定する。1学級の最低人数は、集団生活を通じて「生きる力」の基礎を養うため、経営意識を持った幼稚園運営の観点から、10人を下回ることのないよう保護者ニーズに応じた工夫や努力をする。
・袋井市立幼稚園における適正な学級数
幼児教育においては、より多くの幼児と出会い、多様な関係を構築することによって経験が積めることから、1学年の学級数は複数が望ましい。
・袋井市立幼稚園における統廃合の考え方
今後概ね10年間は1小学校区につき1公立園を存続させていくことが望ましいが、社会情勢や保護者ニーズの動向、幼児期における教育環境の適正規模、財政的状況などの諸条件を見極めながら総合的に判断し、状況の変化に柔軟な対応も必要。
・幼保一元化(認定こども園化)の推進
公立保育所は近隣幼稚園との統合による認定子ども園化を検討する。中学校区を1つの単位として圏域に設定、将来的には圏域内における公立又は私立の認定子ども園の必要性について検討する。
まとめ
殊更に直近の保育定員の量的拡大のみに特化した待機児童対策や、拙速な公立施設の統廃合の判断などにより、子どもたちの育ちの環境や教育・保育の質を低下させることのないよう、基本方針の内容を今後の事業計画に反映させ、本市の地域の特性に応じた子育て支援施策を推進していく。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。