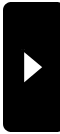2018年02月01日17:14
1月29日、30日静岡商工会議所会館を会場に開催された市町村議会議員研修会(主催㈱自治体研究社)に参加しました。その内容を報告します。
1日目(1月29日)
記念講演「2018年度予算の焦点と自治体政策のポイント」
講師 森裕之(立命館大学政策科学部教授)
1.自治体財政の仕組み
国・地方ともに厳しい財政状況に置かれている状況では、国による自治体誘導政策は強力なものとなり、国は現在も自治体の行政施策を誘導するために、地方財政制度を駆使している。単にそれに迎合するだけであれば、自治体はその根本的役割を果たすことができないだけでなく、後々に深刻な財政危機に陥る可能性が高い。
2.国による地域政策動向
現政権の地方財政への課題は、「地方創生」に向けられている。4つの基本目標をあげているが、地方創生の本質は全国の自治体からみて「時代に合った地域づくりと地域間連携」であり、これはすべての自治体に当てはまる「調整戦略」
と位置づけられている。
「時代に合った地域づくり」とは、端的に言えば、人口減少化において国や自治体の財政負担ができるだけ少なくてすむような地域の再編を行うことである。
それは、居住地域のコンパクト化をおしすすめ、規模の経済性を図り、財政効率を高めようとするものである。その具体的制度として「立地適正化計画」や「小さな拠点」などがつくられている。あくまでもこれは「政策誘導」でしかない。
国が補助金や規制緩和などで実現を促している政策課題は、公共施設の統廃合であり、それとセットで「時代に合った地域づくり」「地域運営組織」の設置・運用促進を求めている。
3.2018年度予算の焦点
①公共施設等の適正管理の推進、②まち・ひと・しごと創生事業費の確保、③歳出特別枠の廃止及び必要な歳出の確保の3つである。
国の姿勢は、自治体へ成果主義へのシフトを強める、明確な根拠に基づく政策づくりを求め、効率性と確実性の高い政策を最重視している。
4.自治体政策のポイント
2018年度予算を含めた今後の地方財政は、地方創生を柱に動いていくことになる。その大枠は「経済・財政再生計画」によって規定されている。
今後の議会における自治体政策の議論のポイント
①政府の動きと自治体の財政制度との関係をチェックする。
②自治体の歳出・歳入の運用実態をチェックする。
③「地方創生」への誘導をうまく利用する。
④地域の特徴・資源とビジョンに基づいた自治体政策を展開する。
⑤明確な根拠に基づく取り組みを心がける。
⑥地元の企業や地域団体の社会的経済力を引き出す施策を適切に取り入れる。
⑦公共施設の再編問題へ対応する。
所感
講師は地方財政の専門家であり、自治体財政の仕組みについて大変解りやすく解説してくれた。国からの押し付けがあるとは言うものの、自治体の実践的なアイデアが大事で、国の制度を利用することも必要との話は参考となった。
2日目(1月30日)
選科A「2018年度の介護保険制度・医療保険制度改正と自治体の課題」
講師 服部万里子(服部メディカル研究所所長)
1.2017年介護保険法改正は社会保障制度見直しに通じる
介護保険法の5度目の改正が平成29年5月に国会通過、今年4月から制度・報酬改定が実施となる。今回の特徴は以下の7点である。
①保険者(市町村)の自立支援・重度化防止の実績評価により交付金を出す、税制インセンティブを設けること。
②介護療養型病床は6年間の猶予を与えて介護療養院に移行させる。
③地域共生社会の実現を図るとして、障害福祉・児童福祉も介護事業指定する。
④所得により火愛護保険に3割負担を導入、高額介護費も見直しアップに。
⑤被用者保険等の介護給付、支援給付を標準報酬総額に変わる。
⑥有料老人ホームの指定取り消しの権限を市町村に与える。
⑦サービス供給事業者の指定拒否の権限を市町村に与える。要介護認定の有効期間を3年まで延長できるようにする。要支援2と要介護1の審査会判定を簡素化する。
2.2018年診療報酬の動向
4月から、診療報酬は総額0.05プラス、医科0.65アップ、歯科0.69アップ
薬価基準▲1.36%、材料▲0.09の方針が出された。
3.2018年介護報酬改定の動向
平成30年度は介護報酬0.54%プラスとの報道も。しかし、平成29年4月の処遇改善加算で1.14%アップしたためそれを含めるとマイナス改定の可能性も。
2019年消費税アップにより、10年勤続介護福祉士に3.3万円処遇改善が閣議決定されているが、対象者はごくわずかしかいない。
①全国48自治体で地域区分が変更される。
②併設建物、同一建物のサービス事業所は大幅な減算となる。
③訪問介護は生活援助に大きく改訂されサービス低下のおそれも。
④訪問看護は支援と看護で報酬を分けることに。
⑤デイサービスは1時間単位に変更、レスパイト(家族負担の軽減)も減額に。
自立支援は評価・点数化し加算も。
⑥通所リハビリは医師関与条件緩和される。
⑦定期巡回随時対応型訪問看護はオペレータ条件緩和。
⑧福祉用具は全国標準単価を算出し16%アップは自費へ、値下げ競争を煽る。
⑨ケアマネジメントは看取り、退院支援を評価、生活支援援助のケアプランは適正化を強化する。
⑩居宅療養管理指導は同一建物の月の利用者数により減算する。
⑪施設への障がい者の受け入れ促進、機能訓練重視、小規模特養は減算、外泊にサービス提供施設新設。
⑫医療的ケア提供加算を設け、特定施設は医療対応を強化。
⑬認知症のグループホームは痰の吸引など医療行為を評価。
⑭介護報酬で認知症の加算が創設される。
⑮自立支援が評価される。
以上、今回の改正で大変多くの変更が行われます。
4.地域包括ケアと在宅医療・多職種連携
退院支援の具体化がすべての一般病への在宅復帰率で具体化され、病床削減計画との関係で退院が促進されます。介護職に医療行為を認める研修や看護職には医師の指示を得ないで医療行為を認める「特定看護師」養成を進めます。
サービス付き高齢者住宅が、実質的に病院から退院できない人の受け皿に位置付けられています。
5.認知症の国の方針と地域で支える自治体の役割
平成26年、認知症の人は65歳以上の15%に発生、2012年時点で約462万人を上回るとのデータが出された。認知症状を起こす原因疾患は30以上あり、1番多いのがアルツハイマー型認知症で日本では6割を占めている。また介護者による虐待の6割に認知症がある。
以上が解説の主な内容です。
所感
講師の服部さんは、日本ケアマネジメント学会副理事長を務めるなど制度に精通している専門家というだけでなく、自らケアマネージャーとしてケアプランを作成するなど介護現場に携わっている。また渋谷区の介護保険運営協議会委員長を務めるなど地域の連携づくりにも腐心している。そうした現場の実態に通じた人ならではの話をたくさん聞くことができ、大変参考となりました。
研修参加報告書 ≫
カテゴリー
1月29日、30日静岡商工会議所会館を会場に開催された市町村議会議員研修会(主催㈱自治体研究社)に参加しました。その内容を報告します。
1日目(1月29日)
記念講演「2018年度予算の焦点と自治体政策のポイント」
講師 森裕之(立命館大学政策科学部教授)
1.自治体財政の仕組み
国・地方ともに厳しい財政状況に置かれている状況では、国による自治体誘導政策は強力なものとなり、国は現在も自治体の行政施策を誘導するために、地方財政制度を駆使している。単にそれに迎合するだけであれば、自治体はその根本的役割を果たすことができないだけでなく、後々に深刻な財政危機に陥る可能性が高い。
2.国による地域政策動向
現政権の地方財政への課題は、「地方創生」に向けられている。4つの基本目標をあげているが、地方創生の本質は全国の自治体からみて「時代に合った地域づくりと地域間連携」であり、これはすべての自治体に当てはまる「調整戦略」
と位置づけられている。
「時代に合った地域づくり」とは、端的に言えば、人口減少化において国や自治体の財政負担ができるだけ少なくてすむような地域の再編を行うことである。
それは、居住地域のコンパクト化をおしすすめ、規模の経済性を図り、財政効率を高めようとするものである。その具体的制度として「立地適正化計画」や「小さな拠点」などがつくられている。あくまでもこれは「政策誘導」でしかない。
国が補助金や規制緩和などで実現を促している政策課題は、公共施設の統廃合であり、それとセットで「時代に合った地域づくり」「地域運営組織」の設置・運用促進を求めている。
3.2018年度予算の焦点
①公共施設等の適正管理の推進、②まち・ひと・しごと創生事業費の確保、③歳出特別枠の廃止及び必要な歳出の確保の3つである。
国の姿勢は、自治体へ成果主義へのシフトを強める、明確な根拠に基づく政策づくりを求め、効率性と確実性の高い政策を最重視している。
4.自治体政策のポイント
2018年度予算を含めた今後の地方財政は、地方創生を柱に動いていくことになる。その大枠は「経済・財政再生計画」によって規定されている。
今後の議会における自治体政策の議論のポイント
①政府の動きと自治体の財政制度との関係をチェックする。
②自治体の歳出・歳入の運用実態をチェックする。
③「地方創生」への誘導をうまく利用する。
④地域の特徴・資源とビジョンに基づいた自治体政策を展開する。
⑤明確な根拠に基づく取り組みを心がける。
⑥地元の企業や地域団体の社会的経済力を引き出す施策を適切に取り入れる。
⑦公共施設の再編問題へ対応する。
所感
講師は地方財政の専門家であり、自治体財政の仕組みについて大変解りやすく解説してくれた。国からの押し付けがあるとは言うものの、自治体の実践的なアイデアが大事で、国の制度を利用することも必要との話は参考となった。
2日目(1月30日)
選科A「2018年度の介護保険制度・医療保険制度改正と自治体の課題」
講師 服部万里子(服部メディカル研究所所長)
1.2017年介護保険法改正は社会保障制度見直しに通じる
介護保険法の5度目の改正が平成29年5月に国会通過、今年4月から制度・報酬改定が実施となる。今回の特徴は以下の7点である。
①保険者(市町村)の自立支援・重度化防止の実績評価により交付金を出す、税制インセンティブを設けること。
②介護療養型病床は6年間の猶予を与えて介護療養院に移行させる。
③地域共生社会の実現を図るとして、障害福祉・児童福祉も介護事業指定する。
④所得により火愛護保険に3割負担を導入、高額介護費も見直しアップに。
⑤被用者保険等の介護給付、支援給付を標準報酬総額に変わる。
⑥有料老人ホームの指定取り消しの権限を市町村に与える。
⑦サービス供給事業者の指定拒否の権限を市町村に与える。要介護認定の有効期間を3年まで延長できるようにする。要支援2と要介護1の審査会判定を簡素化する。
2.2018年診療報酬の動向
4月から、診療報酬は総額0.05プラス、医科0.65アップ、歯科0.69アップ
薬価基準▲1.36%、材料▲0.09の方針が出された。
3.2018年介護報酬改定の動向
平成30年度は介護報酬0.54%プラスとの報道も。しかし、平成29年4月の処遇改善加算で1.14%アップしたためそれを含めるとマイナス改定の可能性も。
2019年消費税アップにより、10年勤続介護福祉士に3.3万円処遇改善が閣議決定されているが、対象者はごくわずかしかいない。
①全国48自治体で地域区分が変更される。
②併設建物、同一建物のサービス事業所は大幅な減算となる。
③訪問介護は生活援助に大きく改訂されサービス低下のおそれも。
④訪問看護は支援と看護で報酬を分けることに。
⑤デイサービスは1時間単位に変更、レスパイト(家族負担の軽減)も減額に。
自立支援は評価・点数化し加算も。
⑥通所リハビリは医師関与条件緩和される。
⑦定期巡回随時対応型訪問看護はオペレータ条件緩和。
⑧福祉用具は全国標準単価を算出し16%アップは自費へ、値下げ競争を煽る。
⑨ケアマネジメントは看取り、退院支援を評価、生活支援援助のケアプランは適正化を強化する。
⑩居宅療養管理指導は同一建物の月の利用者数により減算する。
⑪施設への障がい者の受け入れ促進、機能訓練重視、小規模特養は減算、外泊にサービス提供施設新設。
⑫医療的ケア提供加算を設け、特定施設は医療対応を強化。
⑬認知症のグループホームは痰の吸引など医療行為を評価。
⑭介護報酬で認知症の加算が創設される。
⑮自立支援が評価される。
以上、今回の改正で大変多くの変更が行われます。
4.地域包括ケアと在宅医療・多職種連携
退院支援の具体化がすべての一般病への在宅復帰率で具体化され、病床削減計画との関係で退院が促進されます。介護職に医療行為を認める研修や看護職には医師の指示を得ないで医療行為を認める「特定看護師」養成を進めます。
サービス付き高齢者住宅が、実質的に病院から退院できない人の受け皿に位置付けられています。
5.認知症の国の方針と地域で支える自治体の役割
平成26年、認知症の人は65歳以上の15%に発生、2012年時点で約462万人を上回るとのデータが出された。認知症状を起こす原因疾患は30以上あり、1番多いのがアルツハイマー型認知症で日本では6割を占めている。また介護者による虐待の6割に認知症がある。
以上が解説の主な内容です。
所感
講師の服部さんは、日本ケアマネジメント学会副理事長を務めるなど制度に精通している専門家というだけでなく、自らケアマネージャーとしてケアプランを作成するなど介護現場に携わっている。また渋谷区の介護保険運営協議会委員長を務めるなど地域の連携づくりにも腐心している。そうした現場の実態に通じた人ならではの話をたくさん聞くことができ、大変参考となりました。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。