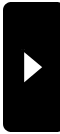2015年08月07日09:54


調査研修報告書
私は8月3日4日、滋賀県大津市の全国市町村国際文化研修所で開催された「第1回市町村議会議員特別セミナー」に参加しました。その内容を報告します。
今回のセミナーは「福祉の取り巻く現状を知り、適切な施策を提案することが地方議員の使命であり、各界で活躍している方々から講演をいただき、今後の福祉のあり方や自治体に求められる役割について考える」との趣旨で開催されました。セミナーには北は秋田、南は沖縄まで、全国から280名の議員の参加がありました。
8月3日(月)
「なぜ地域包括ケアシステムなのか」 東京大学名誉教授 大森 彌(わたる)氏
厚生省「高齢者介護・自立支援システム研究会」座長、厚生労働省社会保障審議会会長などの経歴で明らかなように、厚生労働省と一緒になって介護保険制度の創設やその後の改悪に直接関わっている学者です。その為か、自慢話が多く、費用負担増やサービス利用の制限など制度改悪についても制度維持のためには仕方がないと言い放つ人で、違和感を持ちました。
高齢者の人口増に伴い、独居、高齢者のみ世帯の増加していく。介護サービスのニーズにどうこたえていくかが大きな課題であり「家族同居」モデルから「同居+独居」モデルへの転換と地域包括ケアシステムの確立が必要と、システム構築の必要性をもっぱら高齢者の人口増への対応として描き、自治体に責任を転嫁する論調を素直に受け入れることはできませんでした。
「三鷹市がすすめる協働による地域福祉とコミュニティ創生」 東京都三鷹市長 清原慶子 氏
清原市長は、学生時代から市の基本計画作りに「市民参加」、慶応大学など研究者としても審議会に関わるなどの経験を持ち、平成15年に市長に就任、現在4期目となっている。三鷹市は、旧来の地縁組織による「ムラ」が崩壊するという都市自治体共通の問題に対して、古くから住み続けている市民と新しく転入した市民とが「地域性」と「共同性」を育むために、7つのコミュニティ住区ごとにコミュニティセンターを拠点とした市民による「住民協議会」の活動を推進する「コミュニティ再生」といえる自治体政策モデルを推進してきた。
今自治体へ求められている「地域包括ケアシステム」の確立も、住民本位の地域づくりの延長にあるとの考えから、住民協議会を基盤とした「地域ケアネットワーク」を展開し、健康づくり活動と平行して介護予防事業などを住民参加で行なっている。住民協議会には住民組織だけでなくNPO、地域企業も参加し、協働で「地域サロン」の運営、ボランティアの育成、「見守りネットワーク」など各種事業を展開している。介護保険制度改正で求められている「新しい総合事業」にとどまらず、幅広い視点で、住民との協働で地域福祉を展開していく三鷹市の進め方は、学ぶべき点が多く大いに参考となる講演でした。
8月4日(火)
「チャイルド・プア~子どもの貧困から見えてきたこと~」 NHK報道番組ディレクター 新井直之 氏
新井氏はNHK入局後一貫してドキュメンタリー製作部門を歩み、現在は「クローズアップ現代」や「NHKスペシャル」の政策に携わっている。
講演では、製作した番組の一部を流すなど、貧困の中で苦しむ子どもの様子、それに取り組むケースワーカーの姿など現場の実態がリアルに伝わる内容で、解決には国の抜本的な政策強化が必要なことも明らかにした。
新井氏は「子どもの貧困の問題は、制度の問題であり、大人の責任でもある。ライフワークとして今後も携わって生きたい」と強い意志を示した。また「現在のHHKは上層部の姿勢もあって、製作現場は萎縮している。不作為で目をそらすようなことをしてはいけない。」と取り巻く環境への不満も述べた。こうした良心的メディアの役割は大きく、精一杯取り組んでいる放送現場の人を守り支援していかなければと改めて感じた。
「知的障害者に導かれた企業経営から皆働社会実現への提言」 日本理化学工業株式会社会長 大山泰弘 氏
日本理化学工業は従業員80人のチョーク製造会社。1960年に始めて知的障害者を雇用して以来、一貫して障害者雇用を推し進めてきた。1975年には、川崎市に日本発の知的障害者多数雇用モデル工場を建設。現在80人の社員のうち60名が知的障害者(障害者雇用割合約7割)。製造ラインはほぼ100%知的障害者のみで稼動できるよう、行程にさまざまな工夫を凝らしている。こうした経営が評価され、2009年渋沢栄一賞を受賞した。
病気の父の後を継ぐため、先生になりたかったが大学卒業後そのまま入社。その後どうして障害者と関わるようになったのか、現在に至るまでの道のりを話された。人間の究極の幸せは、人に愛されること、ほめられること、人の役に立つこと、必要にされることの4つであり、障害者も同様。障害者は施設で一生過ごすより仕事ができる幸せを感じ、雇用賃金に補助しても中小企業に任せれば福祉の費用は半分以下となる。誰もが働く社会を実現したい。人の幸せのために働けば、その幸せは自分に戻ってくると、人との出会いも前向きにとらえ、会社の経営も「おかげでと」、常に感謝の心を忘れない大山社長の優しい的をえたお話は、社会のあり方を根本見直せば、もっと障害者にとっても暮らしやすい社会の実現は可能であると参加者に感動を呼ぶ内容でした。
感想・参考となった点
三鷹市の地域ケアネットワーク構築、福祉活動推進の取組は、都市部の住民の連帯を構築するという困難なところから始めながら成果を上げている。袋井市は地方都市でありコミュニティもしっかりしていて市民活動も熱心であり、袋井市のレベルなら十分可能であり、大いに参考にすべきだと思います。
NHKディレクターの子どもの貧困の話は、現場が見えづらく実態をつかむことは大変ですが、学校、福祉の現場と協力し対処すべき重要な課題であると思います。大山氏の述べた障害者雇用については、先進事例として学ぶ点も多く、行政としてもできる限りの取組を求めたいと思います。
三鷹市長清原慶子氏の講演を聞く。≫
カテゴリー
調査研修報告書
私は8月3日4日、滋賀県大津市の全国市町村国際文化研修所で開催された「第1回市町村議会議員特別セミナー」に参加しました。その内容を報告します。
今回のセミナーは「福祉の取り巻く現状を知り、適切な施策を提案することが地方議員の使命であり、各界で活躍している方々から講演をいただき、今後の福祉のあり方や自治体に求められる役割について考える」との趣旨で開催されました。セミナーには北は秋田、南は沖縄まで、全国から280名の議員の参加がありました。
8月3日(月)
「なぜ地域包括ケアシステムなのか」 東京大学名誉教授 大森 彌(わたる)氏
厚生省「高齢者介護・自立支援システム研究会」座長、厚生労働省社会保障審議会会長などの経歴で明らかなように、厚生労働省と一緒になって介護保険制度の創設やその後の改悪に直接関わっている学者です。その為か、自慢話が多く、費用負担増やサービス利用の制限など制度改悪についても制度維持のためには仕方がないと言い放つ人で、違和感を持ちました。
高齢者の人口増に伴い、独居、高齢者のみ世帯の増加していく。介護サービスのニーズにどうこたえていくかが大きな課題であり「家族同居」モデルから「同居+独居」モデルへの転換と地域包括ケアシステムの確立が必要と、システム構築の必要性をもっぱら高齢者の人口増への対応として描き、自治体に責任を転嫁する論調を素直に受け入れることはできませんでした。
「三鷹市がすすめる協働による地域福祉とコミュニティ創生」 東京都三鷹市長 清原慶子 氏
清原市長は、学生時代から市の基本計画作りに「市民参加」、慶応大学など研究者としても審議会に関わるなどの経験を持ち、平成15年に市長に就任、現在4期目となっている。三鷹市は、旧来の地縁組織による「ムラ」が崩壊するという都市自治体共通の問題に対して、古くから住み続けている市民と新しく転入した市民とが「地域性」と「共同性」を育むために、7つのコミュニティ住区ごとにコミュニティセンターを拠点とした市民による「住民協議会」の活動を推進する「コミュニティ再生」といえる自治体政策モデルを推進してきた。
今自治体へ求められている「地域包括ケアシステム」の確立も、住民本位の地域づくりの延長にあるとの考えから、住民協議会を基盤とした「地域ケアネットワーク」を展開し、健康づくり活動と平行して介護予防事業などを住民参加で行なっている。住民協議会には住民組織だけでなくNPO、地域企業も参加し、協働で「地域サロン」の運営、ボランティアの育成、「見守りネットワーク」など各種事業を展開している。介護保険制度改正で求められている「新しい総合事業」にとどまらず、幅広い視点で、住民との協働で地域福祉を展開していく三鷹市の進め方は、学ぶべき点が多く大いに参考となる講演でした。
8月4日(火)
「チャイルド・プア~子どもの貧困から見えてきたこと~」 NHK報道番組ディレクター 新井直之 氏
新井氏はNHK入局後一貫してドキュメンタリー製作部門を歩み、現在は「クローズアップ現代」や「NHKスペシャル」の政策に携わっている。
講演では、製作した番組の一部を流すなど、貧困の中で苦しむ子どもの様子、それに取り組むケースワーカーの姿など現場の実態がリアルに伝わる内容で、解決には国の抜本的な政策強化が必要なことも明らかにした。
新井氏は「子どもの貧困の問題は、制度の問題であり、大人の責任でもある。ライフワークとして今後も携わって生きたい」と強い意志を示した。また「現在のHHKは上層部の姿勢もあって、製作現場は萎縮している。不作為で目をそらすようなことをしてはいけない。」と取り巻く環境への不満も述べた。こうした良心的メディアの役割は大きく、精一杯取り組んでいる放送現場の人を守り支援していかなければと改めて感じた。
「知的障害者に導かれた企業経営から皆働社会実現への提言」 日本理化学工業株式会社会長 大山泰弘 氏
日本理化学工業は従業員80人のチョーク製造会社。1960年に始めて知的障害者を雇用して以来、一貫して障害者雇用を推し進めてきた。1975年には、川崎市に日本発の知的障害者多数雇用モデル工場を建設。現在80人の社員のうち60名が知的障害者(障害者雇用割合約7割)。製造ラインはほぼ100%知的障害者のみで稼動できるよう、行程にさまざまな工夫を凝らしている。こうした経営が評価され、2009年渋沢栄一賞を受賞した。
病気の父の後を継ぐため、先生になりたかったが大学卒業後そのまま入社。その後どうして障害者と関わるようになったのか、現在に至るまでの道のりを話された。人間の究極の幸せは、人に愛されること、ほめられること、人の役に立つこと、必要にされることの4つであり、障害者も同様。障害者は施設で一生過ごすより仕事ができる幸せを感じ、雇用賃金に補助しても中小企業に任せれば福祉の費用は半分以下となる。誰もが働く社会を実現したい。人の幸せのために働けば、その幸せは自分に戻ってくると、人との出会いも前向きにとらえ、会社の経営も「おかげでと」、常に感謝の心を忘れない大山社長の優しい的をえたお話は、社会のあり方を根本見直せば、もっと障害者にとっても暮らしやすい社会の実現は可能であると参加者に感動を呼ぶ内容でした。
感想・参考となった点
三鷹市の地域ケアネットワーク構築、福祉活動推進の取組は、都市部の住民の連帯を構築するという困難なところから始めながら成果を上げている。袋井市は地方都市でありコミュニティもしっかりしていて市民活動も熱心であり、袋井市のレベルなら十分可能であり、大いに参考にすべきだと思います。
NHKディレクターの子どもの貧困の話は、現場が見えづらく実態をつかむことは大変ですが、学校、福祉の現場と協力し対処すべき重要な課題であると思います。大山氏の述べた障害者雇用については、先進事例として学ぶ点も多く、行政としてもできる限りの取組を求めたいと思います。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。