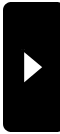2009年12月18日13:33
 昨日、袋井地域産業イノベーション事業として取り組まれている「農業経営塾」に参加しました。
昨日、袋井地域産業イノベーション事業として取り組まれている「農業経営塾」に参加しました。 今回参加したのは、テーマは「成功事例から見た農業経営のあり方」でしたが、報告の内容が「たかしま有機農法研究会」の取組みで関心があったからです。同研究会は、滋賀県高島市で有機農法により稲作に取組み、生産したお米を「たかしま生き物田んぼ米」とブランド化、商標も取得しております。
今回参加したのは、テーマは「成功事例から見た農業経営のあり方」でしたが、報告の内容が「たかしま有機農法研究会」の取組みで関心があったからです。同研究会は、滋賀県高島市で有機農法により稲作に取組み、生産したお米を「たかしま生き物田んぼ米」とブランド化、商標も取得しております。
高島市は琵琶湖の西部に位置し、農業排水も琵琶湖に流れることから、環境負荷に対し世論が敏感な土地柄で有機農業推進モデルタウンにも選定されております。市内農家の16名が参加し2006年から農薬化学肥料不使用の米の栽培に取組み、栽培面積は20haにも広がっています。生産技術の確立への試行錯誤、有機米を付加価値をつけてのマーケティング・販路拡大にも努力して採算ベースに乗せるところまできています。田植え時に米ぬかを散布し、雑草を抑える、畦草も除草剤を使わない、冬季湛水、中干しを遅らすなど生物に配慮した生産管理で多くの生物の生育場所として共生を図っていて、それが消費者の評価につながり信頼を得ています。「生物多様性」「有機農法推進」など時代の流れに沿ったものですが、実際にそれを実践するには多くの課題があります。成功事例といってもまだ発展途上にありますが、取り組んでいる農家のみなさんがやりがいを感じて取り組んでいることに好感を持てました。 作目は違っても同じ農家として、勇気を持って減農薬など環境にやさしい農業に取り組まなくてはと、意を新たにしました。
作目は違っても同じ農家として、勇気を持って減農薬など環境にやさしい農業に取り組まなくてはと、意を新たにしました。
「たかしま生き物田んぼ米」の報告を聞きました。≫
カテゴリー │農業経営
 昨日、袋井地域産業イノベーション事業として取り組まれている「農業経営塾」に参加しました。
昨日、袋井地域産業イノベーション事業として取り組まれている「農業経営塾」に参加しました。 今回参加したのは、テーマは「成功事例から見た農業経営のあり方」でしたが、報告の内容が「たかしま有機農法研究会」の取組みで関心があったからです。同研究会は、滋賀県高島市で有機農法により稲作に取組み、生産したお米を「たかしま生き物田んぼ米」とブランド化、商標も取得しております。
今回参加したのは、テーマは「成功事例から見た農業経営のあり方」でしたが、報告の内容が「たかしま有機農法研究会」の取組みで関心があったからです。同研究会は、滋賀県高島市で有機農法により稲作に取組み、生産したお米を「たかしま生き物田んぼ米」とブランド化、商標も取得しております。高島市は琵琶湖の西部に位置し、農業排水も琵琶湖に流れることから、環境負荷に対し世論が敏感な土地柄で有機農業推進モデルタウンにも選定されております。市内農家の16名が参加し2006年から農薬化学肥料不使用の米の栽培に取組み、栽培面積は20haにも広がっています。生産技術の確立への試行錯誤、有機米を付加価値をつけてのマーケティング・販路拡大にも努力して採算ベースに乗せるところまできています。田植え時に米ぬかを散布し、雑草を抑える、畦草も除草剤を使わない、冬季湛水、中干しを遅らすなど生物に配慮した生産管理で多くの生物の生育場所として共生を図っていて、それが消費者の評価につながり信頼を得ています。「生物多様性」「有機農法推進」など時代の流れに沿ったものですが、実際にそれを実践するには多くの課題があります。成功事例といってもまだ発展途上にありますが、取り組んでいる農家のみなさんがやりがいを感じて取り組んでいることに好感を持てました。
 作目は違っても同じ農家として、勇気を持って減農薬など環境にやさしい農業に取り組まなくてはと、意を新たにしました。
作目は違っても同じ農家として、勇気を持って減農薬など環境にやさしい農業に取り組まなくてはと、意を新たにしました。※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。